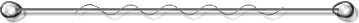
● NGO実習 ●
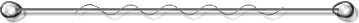
<京王バス改善班>
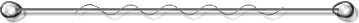
<EGG DOME CAFE>
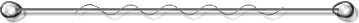
● NGO実習!?事始め ●
勤務先の大学で、「NGO実習」というオープン・サブゼミを始めた。サブゼミとは、正規の授業のゼミナールの時間とは別の時間を使った勉強会。教員の側には、サービス残業。オープンがついていると、ゼミの受講生でなくとも、だれでも参加できる。ようするに、NGOに興味のある人を集めて、自主的な勉強会をはじめたというわけだ。
ところで「実習」って何? そう。ただの勉強会ではなく、実際にNGOを作って、動かしてみよう、というのだ。一般に、自然科学と違って、社会科学では、実験はできないとされている。
ところが、限定的な規模で、社会実験と称するものができないわけではない。ある町を決めて、カードマネーの使用実験をするなんてのは有名だろう。新製品が北海道でいち早く売りに出されて、売れ行きが調査されるというのも、その道のひとには有名なのだ。
NGOということばは、ずいぶんいろいろな意味で使われるようになったが、ぼくは、それに独特の意味をこめてみようと思っている。「無責任なおせっかいやだが、ちょっとすみにはおけないことを言ったり、やったりする人たち」。これがいまぼくが考えているNGOの定義だ。
いっぱんに、責任者というのは、無能な人が多い。責任の重さに打ちひしがれて無能になるのだ。おれが責任者だ、と思うだけで、ほかの人々の発言がすべて無責任に思え、聞く耳を失ってしまう。こんな責任者がエリートと言われてきた。
NGOの活動は、そんな責任者を頂点とする官僚機構の無能ぶりに耐え兼ねた責任者ではない人々(ほんとうは主権者のはずの市民!)のひまとおせっかいな情熱とから生まれた。閑がない人にNGO活動はできない。おせっかいでない人、つまり自分の利益だけを考える人は、よその責任者の管轄に口出しなどしないものだ。
ところで、20世紀末のこの世界的なNGOの氾濫は、ひまとおせっかいの情熱にみちた市民が、下から、官僚機構に蝕まれた社会を再建しようという動きだといえないだろうか。
ともあれ、キャンパスの食文化の改善をターゲットにした小さな社会実験はすでに始められた。またその経過を報告させていただきます。
下に、参考資料として、先週の最初の集まりで配布されたコンセプト・ペーパーを収録しておきます。
(2000年5月22日)
:::::参考資料:::::
NGO実習:基本コンセプト(オープンゼミ2000;ただしゼミ提供)
<NGO>
1 世界的に新しい社会現象として注目し、独自に定義したい(文献参照)。広い意味での人権問題について、調査・政策提言・世論喚起(キャンペーン)・ロビー活動(関係する諸機関の担当者への働きかけ)をやり、関係するあらゆる人々が問題を解決する力を身につける手助けをする組織としてのNGO。(公的な統治機関governmental organizationの外にあって、empowermentのための触媒となることをめざす民間非営利公益団体)
2 大学のキャンパス内の問題について、学内NGOの立ち上げ・活動・解散の実験を行い、NGO活動のインパクトを観察・測定・評価する。(参加者で共同レポートやビデオ・ドキュメンタリーを作成)
3 自分も参加した活動を冷静に観察することはむずかしい。だが身近で切実な問題を解決できないような学問に情熱を燃やせる人がいるだろうか。
<キャンパスの食文化>
1 学生、教職員などの間でのキャンパス食文化への漠然とした不満。高い、まずい、席がない。・・・安全か、健康か、楽しいか。・・・ああ生まれてきてよかった!思わず口元がほころび歓喜のため息のもれる味。第3世界の飢餓や環境破壊、次世代にまで蓄積される化学物質や操作された遺伝子のことに思いを馳せながら、ゆっくり噛みしめ、味わえるような食事。愛と学問が花開く出会いと語り合いの食卓。そんな食文化が多摩キャンパスにあるだろうか。
2 貧しい食生活は人生の一大事すなわち人権問題である。多摩キャンパスの食文化は、この点でかなり問題がある。
3 学内NGO「多摩キャンパスにすてきな食文化をつくるネットワーク(仮称)」を作り、問題解決のための行動を起こす。そのようなNGO活動を社会実験として記録・研究・議論したい。とりあえず、ニュースを出して、議論をまきおこし、世論を作りたい。 可能なところから、生協や食堂、大学の部局などにはたらきかけていきたい。
<これまでの議論ででたコンセプト>
エッグドームをUniversity Club Houseにする。(5Fホールのライブハウス化) エッグドーム食堂のエスニック・Organicカフェ化。夜の音楽とお酒。 学内に、雰囲気のある、しゃれたコンパ会場を!(エッグドーム2F、あるいは?) 社学センタープラザやその周囲にテーブルとイスを置いてオープン・カフェに。現カフェの内装、メニューの改造。
東南アジア式のFood Center あるいはFood Courtのイメージ:手ごろな値段での多様なエスニック料理(多品種少量注文生産)
安全な食品、食材の供給。バーベキューから、なべものまでの、自炊(半自炊)コーナー。
以上。