■2013年7月20日、立命館大学衣笠キャンパスで行われた「主権と空間」研究会で「領土の喪失/故郷の喪失 戦後ドイツにおける被追放者たちの政治」を報告しました。
ドイツ現代史の高橋秀寿さんが科研費をとって主催されている研究会での報告です。今回は日露関係とや北方での境界領域の研究をなさっている麓慎一さん(新潟大学)がコメンテーターとして参加してくださいました。「被追放者」とは、第二次大戦末期から1950年までに中東欧から強制的に移住を強いられた1200万を超える「ドイツ人」のことです。東方領土喪失の「当事者」であった彼らの「故郷権」をめぐる活動や主張、そして彼らの存在それ自体が、戦後ドイツの東方国境紛争を単なる国境線画定の問題にとどまらない、「人」の権利や記憶・文化の問題にしているということについて話をしました。ドイツの東方国境が解決されたのは、国境線問題と「人」の問題を切り離すことによって可能になったとみることができます。それはまた、国境線問題解決後も「人」の問題は残るということもでもあります。現在被追放者の包括的団体である「被追放者連盟」が「追放」の歴史展示にこだわっていることも、そこから来ています。
被追放者連盟会長であるエリカ・シュタインバッハが1999年に発表した「反追放センター」は、ポーランドのみならず、国内からも批判をうけました。しかしその後の粘り強い努力と、譲歩できる部分は譲歩し、ようやく「追放のドキュメントセンター」をベルリンに建設することがきまりました。昨月その着工が始まりました。メルケル首相の強い支持のもと、ポーランドもそれを黙認している状況です。
今後「追放」の後に残った被追放者の「故郷」をめぐる記憶や文化がどのようにドイツ史の一部として残留していくのかどうか、見ていきたいと思っています。
■2013年6月22日、御茶ノ水女子大学・共通講義棟2号館で行われた第29回日本ドイツ学会シンポジウムにおいて、「領土と国益――ドイツ東方国境紛争から日本を展望する」を報告しました。
「日本ドイツ学会」とは、ドイツ語圏を主たるフィールドとしている研究者が学際的に集まっている団体で、設立は1985年だそうです。このような学会が30年近くも続けられ、現在でも大学院生や若手研究者からベテランまで参加しています。「ドイツ研究」の層の厚さとそのコミットメントを実感させられます。
シンポジウムは午後1時半から行われました。私以外の報告者は吉岡潤さん(津田塾大学)、藤田恭子さん(東北大学)、広渡清吾さん(専修大学)、そしてラインハルト・ツェルナーさん(ボン大学)で、コメンテーターは川喜田敦子さん(中央大学)、司会は姫岡とし子さん(東京大学)、足立信彦さん(東京大学)でした。
私の報告では、第二次大戦後、ドイツ連邦共和国がオーデル=ナイセ線を承認し、東方領土を放棄した経緯を簡単に話した後、日本がかかえる国境線問題との相違について考察しました。当日配布したレジュメがこれです。この内容を論述した文章が、来年度の『ドイツ研究』に掲載されることになっています。
シンポジウムには100名を超える人が出席し、盛況でした。大学の研究者ばかりでなく、新聞社の方も参加されていました。 当日のプログラムに関する詳細はこちらをどうぞ。→
■「ドイツの排外主義 −「右翼のノーマル化」のなかで」を2013年4月28日(日)の国家論研究会で報告しました。
これは『移民・ディアスポラ研究』第3号(近刊)に寄稿した論文の内容に即したものです。ヨーロッパで拡大する「右翼ポピュリズム」の動向のなかでドイツの排外主義(右翼ポピュリズムの台頭)を検討したものです。論文の方も、近日中に出版されることになっています。
報告の趣旨を転載しておきます。
≪21世紀に入ってフランスやオランダ、スイスや北欧諸国等多くのヨーロッパ諸国で反移民・反ヨーロッパ統合を掲げる右翼ポピュリスト政党が支持をのばしている。これらの右翼政党は、その主張や政治スタイルにおいて従来の「極右」とは区別される。またその支持基盤は、保守政党支持層や労働者階級へと広がり、社会のメインストリームにまで及んでいる。このような最近のヨーロッパにおける右翼の変化を、社会学者のメーベル・ベレジンは「右翼のノーマル化」と呼んでいる。そのようななかにあって、ヨーロッパのほぼ中央に位置するドイツでは、現在のところ有力な右翼ポピュリスト政党が存在していない。しかしそれは、ドイツに「右翼のノーマル化」が及んでいないことを意味するわけではない。
この報告では、先ずユーロバロメーターの結果を参照しながら、「右翼のノーマル化」の背後にあるヨーロッパの人々の移民に対する態度の変化を概観し、その後でドイツにおける2010年以後の右翼ポピュリズムの状況を、「ザラツィン論争」の経緯を追いつつ検討する。全体を通じて、国家の機能不全による社会的セキュリティ不安の増大が「右翼のノーマル化」につながっているという仮説を提示することで、今後の右翼ポピュリズム研究の導入としたい。≫
■「国家の形成――ヴェーバー、ティリー、ブルデュー (国家の社会学にむけた一試論)」を2012年8月5日の国家論研究会において報告しました。
最近取り組んでいる国家論研究の中間報告のようなものです。国家=実在論の観点から、国家がもつ固有な能力をどうとらえるのかというのがテーマです。以下、報告の概要を転載しておきます。
≪われわれが国家につて語る際、そこでは国民国家のことが念頭に置かれることが多い。しかし「国家(state)」と「国民(nation)」とは、概念的にも制度的にもまったく異なった系譜をもっている。国民がどのように想像されようと、国家は武力を保持し、法を執行し、刑罰を科し、税を徴収し、徴収した財源を「公共」の名の下に使用する能力をもった組織として存在している。グローバル経済における国家の役割の低下が言われ、国民の文化的同質性や連帯の喪失が論じられるなかにありながら、現在でも世界の国家の多くはこれらの独自な能力を(多くの場合独占的に)維持し続けている。では、果たしてこのような国家の能力は何に由来するものなのだろうか?
本報告では、「国民(nation-)」という連辞符を取り去った後の、統治組織としての国家それ自体に焦点を当て、国家およびその独自な能力の形成過程についてマックス・ヴェーバー、チャールズ・ティリー、ピエール・ブルデューという3人の社会学者の国家論を参照しながら考察する。そこで目指されるのは、国家形成を物理的、経済的、象徴的諸資源の集中・蓄積の過程へと分解することにより、単一の政治的実体として想定されがちな国家を、徹底して被説明項(explanandum)として再概念化することである。≫
■書評「「異常さ」から見た現実構成――文化社会学のパースペクティブ」(書評対象書:Bernhard Giesen, ZwischenLagen: Das Außerordentliche als Grund der sozialen Wirklichkeit. Velbrück Wissenschaft, 2010)を『現代社会学理論研究』第6号(2012年3月31日発行)に掲載しました。
コンスタンツでの在外研究中にお世話になったギーゼン氏の近著の書評を書きました。ドイツ語なので日本では読者がどうしても限られてしまいますが、ドイツ語の読める方にはぜひ読んでいただきたいと思います。文化社会学的観点から社会的世界の現実構成のされ方について分析したもので、キーワードはこの書評のタイトルで示したように「異常さ」です。既存の認識枠組みで把握不能な「間(あいだ)の事態」としての「異常さ」こそが、現実構成の動因であるというテーゼを、様々な事例をもとに論証しています。私の関心でもある認知図式を介した現実理解の構成という認知社会学的問題に切り込む方法の一つになるだろうと考えています。
また、この書評の最後に、日本の福島原発事故に対するドイツ社会の反応について短い考察を行っています。私はちょうどこの事故の発生時、ドイツに滞在しており、ドイツ社会の異様というべき反応の大きさを身をもって見聞しました。福島の事故がいかに大惨事であったにせよ、ドイツ社会の反応の大きさは世界のなかでも際立っていました。ご存知のようにこれが、ドイツのエネルギー政策の転換を進める決定的原因となったわけですが、私はこれを、リスク社会学者のオルトヴィン・レン(Ortwin Renn)の議論に基づき「リスク認識の変化」という観点から考えています。この問題について、機会があれば、もっと深めて考察してみたいと考えています。
なお、『現代社会学理論研究』は今回から書評欄を置くようになりました。しかも原稿用紙20枚程度のかなり贅沢な量を書くことができました。このような書評の機会を与えていただいた編集委員の方々に感謝いたします。
■「シンボルと大衆ナショナリズム ――ジョージ・L・モッセ『英霊』」を掲載した野上元・福間良明編『戦争社会学ブックガイド 現代世界を読み解く132冊』(ナカニシヤ書房)が2012年3月10日付で公刊されました。
ジョージ・モッセの著作『英霊」の内容を紹介しながら、それを題材に戦争の記憶と大衆化した20世紀ナショナリズムの関係について考察した短い論考です。
モッセの業績は最近のナショナリズム研究の流れの中にはなかなか位置づけにくいものでした。以前書いた「ナショナリズムの理論史」にも、彼の業績に言及することはできませんでした。しかし『大衆の国民化(Nationalization of the Masses)』にしても、この『英霊(Fallen Soldiers)』にしても、実に鮮やかにナショナリズムの「手触り」のようなものを感じさせる名作です。ナショナリズムの怖さや不合理さとともにともに、その抗いがたい魅惑について身をもって経験したことのある人間でなければ書くことのできないものでしょう。その筆致の力は、近代主義とか構築主義などの理論的アプローチの是非を超えたものだといえます。
『英霊』は、すでに翻訳されたこの本の邦題であ、論文の中でもこれに従っています。ですが実のところ、私はこの邦題をあまり適切であるとは考えていません。たしかに日本人にはわかりやすいかもしれませんが、あまりにテーマが「靖国化」されすぎていように思います。やはり原題を直訳して「戦没兵士」の方がよいのではないでしょうか。本書は別に、戦没者の「霊」だけがテーマではないからです。
「戦争社会学」という学問(サブ)領域が確立されているわありませんが、戦争は現在日本の人文社会科学の諸領域で幅広く関心をひいている問題です。第二次大戦の帰結や記憶がいまだに影を投げかけていることを考えれば、決して不思議なことではないでしょう。日本に特徴的な研究テーマとして、今までバラバラに行われてきた諸研究の全体に見取り図をつけようという本書の帰途は大変に貴重なものといえます。
ここで私が紹介しているモッセの『英霊』は、本書の中では「戦争を社会学的に考えるための12冊」の一つに選ばれています。
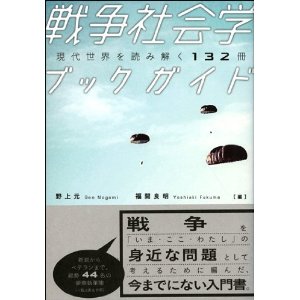
■「日本のナショナリズムの論じ方 ――ケヴィン・M・ドーク『大声で歌え「君が代」』を読む――」を、2011年7月30日、国家論研究会で報告しました。
国家論研究会で、本来予定されていた報告者が一人都合で報告できなかったので、急遽私がピンチヒッターで報告しました。ドークの著作(原題はHiistory of Japanese Nationalism)は、日本のナショナリズムの歴史を包括的に論じたもので、日本のナショナリズムの論じ方自体に新たなアプローチを持ち込もうとした、なかなか野心的なものです。しかし、邦訳は題名も含めかなり問題が多いものでした。本報告では、ドークの議論の基本的な枠組みについて報告したものです。ドークの本に関しては、このHPでも簡単に紹介しています(⇒)。また、当日配布したレジュメを載せておきます(⇒)。
■「『非移民国』時代のドイツの移民政策とそのディスコース」を2011年5月29日、国家論研究会で報告しました。
私自身が数年前から主催してきた国家論研究会での、ドイツから帰国後第一回目の報告でした。1970年代から90年代にかけて、「ドイツは移民国ではない」といってた時代のドイツ連邦共和国の移民統合をめぐるパブリック・ディスコースを考察しました。それをここでは、「エスニックな自己理解とリベラルでポストナショナルな自己理解の拮抗と共存」という角度から論じています。ドイツでの在外研究の成果の一部です。『社会志林』での発表してきた論文と合わせ、また50年代から60年代にかけて、連邦共和国が積極的に外国人労働者を受け入れていた時代のディスコースに関する考察を加えて、まとまったものにする予定でいます。
■「「統合の国』ドイツの統合論争 −変化するドイツ社会の自己理解−」を『社会志林』第57巻第4号(2011)に掲載しました。
国籍法改正後、2000から2010年にかけて進展したドイツの移民統合政策の変遷を、ドイツ社会の自己理解の変化と関連させて分析しました。使っている題材は、新聞や雑誌、議会討論における様々なディスコースです。
これも在外研究の研究成果の一部です。
■ 'From "Non-Imigration Country" to "Country of Integration"'を2010年10月9日、第十回ドイツ‐日本社会科学学会(German-Japanese Society for Social Scineces)で報告しました。
学会は10月8日から10日にかけて法政大学市ヶ谷キャンパスにあるボアソナードタワー26階にある大会議室で行われました。報告は1980年代から2000年代にかけてのドイツの移民統合問題に関するディスコースの変遷を考察したものです。この報告は、ドイツで在外研究中に一時帰国して行いました。ドイツで研究の成果の一部です。(会議で配布したペーハー⇒)
■2009年4月より2011年3月まで、ドイツのコンスタンツ大学において在外研究に従事しました。
コンスタンツ大学ではベルンハルト・ギーゼン(Bernhard Giesen)という文化社会学・歴史社会学を専門にし、集合的アイデンティティや集合的記憶などを研究している社会学者が教授として教鞭をとっています。ギーゼンや彼の研究協力者(Wissenschaftliche Mitarbeiter)達と交流しつつ、「文化社会学(Kultursoziologie)の理論や方法を学びつつ、ドイツにおける移民統合と国民的自己理解の関係について研究を行う予定です。
この研究は1970年代以後、ドイツ連邦共和国において移民の統合が問題になって以来、移民統合とドイツ社会の自己理解がどのように変遷してきたのかを、主として公共的なディスコースの分析を通じて明らかにしようというものです。
それと関連して、研究の分析枠組みとなる文化理論の理論的な研究も並行して行っていこうと思っています。
※在外研究中に書いていたブログです。→
■「文化社会学の課題 −文化の社会理論に向けて−」を『社会志林』第56巻4号(2010)に掲載しました。
下記の論文同様、ドイツでの在外研究の成果の一部です。特に2009年夏から暮れにかけて「文化社会学」の諸理論について色々と勉強しました。その結果を私なりに整理したものです。ただ、このような研究の方向性に、将来どのくらいの可能性があるのか、実際のところ自分でもよく分かりません。
また、最近の社会学系の論文とは異なり「人文系」の論文のスタイルで書いています。参考文献に略号を使わず、文献のタイトルをすべて注に記載し、参考文献リストは掲載しないという、とても“reader unfriendly”なものです。
■「国民国家と移民の統合 −欧米先進諸国における新たな「ネーション・ビルディング」の模索−」が『社会学評論』第60巻第3号(2009)に掲載されました。
日本社会学会の機関紙『社会学評論』において企画された「グローバリゼーション再考」というテーマの特集のための論文として、編集委員の方の依頼によって執筆したものです。現在やっているドイツの移民統合問題の歴史的背景を整理するという意図がありました。ドイツでの在外研究の成果の一部でもあります。また、昨今の「グローバリゼーション」論に関する私なりの疑問も表明されています。
雑誌にも載せた論文の要旨を再録しておきましょう。
「1990年代以後、欧米先進諸国の移民統合政策が変化してきている。それまでの「デニズンシップ」や「多文化主義」に傾斜した政策が後退し、「統合」という概念により重点が置かれるようになっている。それは一見,「グローバル化」時代のトレンドと矛盾するように見える。本論文は、このような最近の変化を、19世紀以来の国民国家形成とグローバルな移民の拡大との歴史的な連関関係の中で考察してみる。国民国家は、19世紀以来200年間のグローバルな変容のなかで形成/再形成され、またグローバルに波及してきた。そのような中で国民国家は、移民を包摂・排除しながらその制度とアイデンティティを構築してきた。本論文は,その歴史的過程を明らかにした上で、最近の欧米先進諸国の「市民的」な移民統合政策への変化が、「異質」なエスノ文化的背景をもった移民系住民を包摂する形で国民国家を再編成しようとする、あらたな「ネーション・ビルディング」への模索であるということを主張する。最後に、こうした最近の欧米先進諸国における変化から日本の状況を簡単に検討する。」
■「ナショナリズムの理論史」を掲載した大澤真幸・姜尚中編『ナショナリズム論・入門』(有斐閣)が2009年8月末に刊行されました。
ナショナリズム研究のテキストです。大学生・大学院生、研究者、その他ナショナリズムに関心を持つ一般読者向けに、様々な著者が様々な視点からナショナリズムについて論じた本です。私が担当しているのはその中の第1章で、題名が示すように、これまでのナショナリズム研究の理論的な視座について、なるべく分かりやすく整理してみました。

■編著『ナショナリズムとトランスナショナリズム――変容する公共圏』が法政大学出版局から3月末(2009年)に刊行されました。
ナショナリズムを主たるテーマとして2006年から毎年一回づつのペースでやってきた「国家論研究会」での報告をベースにした15人の著者が書いた論文からなる論文集です。法政大学社会学部の教員の研究書シリーズである「現代社会研究叢書」の2巻として、また法政大学社会学部教員を中心として行っている科研費の研究プロジェクト「公共圏と規範理論」の研究成果シリーズの第1巻として刊行されたものです。

目次を紹介しておきましょう。
はじめに −本書の課題−
佐藤 成基
第一部 ナショナリズムと理論と概念
第1章 国家/社会/ネーション
―方法論的ナショナリズムを越えて―
佐藤 成基
第2章 チャールズ・テイラーにおける「言語共同体」の限界と可能性
―多文化主義・ナショナリズム・公共圏―
明戸 隆浩
第3章 国家と社会の概念系譜学的素描
左古 輝人
第二部 歴史の中のナショナリズム
第4章 ポピュラー・プレスとファシズム
―戦間期英国におけるファシスト的公共圏とその限界―
津田 正一郎
第5章 国民史教育と「100パーセントアメリカニズム」
―戦間期アメリカにおける在郷軍人会と「公共の記憶」―
望戸 愛果
第6章 ナショナリズムの「想像の公共圏」
―ロシア・シオニズムにおける「国際規範」の創出と応用−
鶴見 太郎
第7章 近代中国における群衆と公共性
―中華民国初期の首都建設事業と「人民」のナショナリズム―
穐山 新
第8章 日本人意識の高揚
−土地闘争期沖縄の祖国復帰ナショナリズム―
坂下 雅一
第9章 「レジスタンスから生まれた共和国」
―反ファシズムと戦後イタリアのナショナル・アイデンティティ―
秦泉寺 友紀
第10章 黄金の扉(ゴールデン・ドアー)」は再び開かれたのか?
―19世紀末中国系移民への生得の市民権付与をめぐる一考察―
大井由紀
第11章 日本の移民政策とネーションのゆくえ
佐々木 てる
第三部 トランスナショナリズムの可能性
第12章 公共圏と国際移民レジーム
−トランスナショナルな規範を求めて−
樽本 英樹
第13章 日本のトランスナショナリズム
―移民・外国人の受け入れ問題と公共圏―
柏崎 千佳子
第14章 愛国心・郷土・公共性
―柳田国男の郷土教育批判とその可能性―
武田俊輔
第15章 〈民族〉を超える〈部族〉
―「暴力の文化」を克服する公共圏の創出―
岡野内 正
■「「血統共同体」からの決別 −ドイツの国籍法改正と政治的公共圏−」が法政大学社会学部内の雑誌『社会志林』第55巻、第4号(2009年3月発行)に掲載されました。
これはここ3年間科研費を受けて行ってきた1999年ドイツ国籍法改正とナショナル・アイデンティティに関する研究の成果です。単著の方に時間がかかり、なかなかこちらの研究に本格的にとりくむことができなかったのですが、ようやく論文にできました。これをふくらまして3月には成果報告書にし、さらに発展させて著作にしていきたいと考えています。
なお、この論文の内容は、2009年2月月22日に開かれた予定の「国家論研究会』で報告しました。
■『ナショナル・アイデンティティと領土――戦後ドイツの東方国境をめぐる論争』が新曜社から2008年3月28日付けで刊行されました。

最近7年間ほど続けてきた、戦後ドイツの東方領土問題に関する本が、ようやく完成しました。テーマ的にはドイツ現代史ですが、ナショナリズム研究の一般的な分析枠組みの構築も探求しています。タイトルにも現れているように、キーワードは「ナショナル・アイデンティティ」です。
総ページ数は約430ページですが、定価は税込みで4410円です。専門書ですから高いですが、、ページ数の割には値段が抑えられています。
■"Territorial Disputes and National Identity in Postwar Germany: The Oder-Neisse Problems in Public Discourse"を2007年10月6日(土)にサンディエゴで行なわれたGerman Studies Association (GSA)の年次コンフェランスで発表しました。
GSAはアメリカのドイツ研究の学会です。様々な領域の人が集まっているインターディシプリナリーな学会で、今回初めてこの学会で報告しました。セッションは金曜から日曜までの3日間で287のセッションが行なわれ、総数で約1000人が報告をしています。参加者はアメリカとドイツからの人が多いようでしたが、私のようにその他の国から参加した人も多少はいたようです。思ったよりも大きい学会でした。私の報告したのは、"German-Poland, Border Studies"と題されたパネルで、ピッツバーグ大学のRandall Halle教授が中心となって組織されたものです。私が昨年までやってきた東方領土問題の研究を報告するのにはピッタリの場所で、他の報告者の報告も興味深く聞きました。私はこのパネルで報告するために、GSAという学会に入会しました。
その他、今回は色々な意味で「学び」の多い学会報告でした。
GSAについてはホームページで見ることができます。
■「国境を越える「民族」 −アウスジードラー問題の歴史的経緯−」が『社会志林』第54巻第1号(2007年7月発行)に掲載されました。
これは下の研究会報告の報告資料に大幅な加筆修正を加えて論文化したものです。
■「国境を越える「民族」 −歴史的文脈から見たアウスジードラー(東方移民)問題−」を2006年11月26日(日)に法政大学大学院布置ヨーロッパ研究所研究会で報告しました。
同研究所は、EUからの研究資金をもとに設置されている研究所で、本学部の羽場先生が所長をされています。私も研究員の一人に名前を連ねています。(HP: http://side.parallel.jp/europa/index.html)
この報告は、戦後ドイツ連邦共和国が東欧から受け入れてきた「アウスジードラー」(東欧地域からのドイツ人移民)問題を、ドイツの「在外同胞」問題としてとらるという観点から、包括的に整理し、分析したものです。今後の筆者の研究テーマは、1999/2000年の国籍法改正にありますが、アウスジードラー問題は、これまでやっていた東方領土問題と、国籍法問題をつなぐ問題として、私自身の中では位置づけられています。今回は、それをあらためて調べなおし、まとめて見ました。できれば、いずれ論文にしたいテーマです。
■「ベルリン共和国と「ホロコースト」 −変化するドイツのナショナル・アイデンティティー」を戦後思想研究会(2006年11月14日)に報告しました。
「戦後思想研究会」は、学部内の同僚教員を中心にやっている小さな研究会です。2年前に東方領土問題についての報告をしましたが(下記参照)、今回は戦後ドイツ連邦共和国のナショナル・アイデンティティを「ホロコースト・アデンティティ」という概念をキー概念にして考察したものです。この概念は、私の東方領土問題研究の中で用いた概念で、今回の報告ではそれを違った角度から考察しています。問題の中心は、ドイツ統一後に、長い論争の末建設された「ホロコースト警鐘碑」をめぐる国内で議論になります。また最近のドイツのメディアにおけるナチスの過去の表象のありかたについても、多少言及しました。
■"The Eastern Territories and Natinoal Identity in Postwar Germany"を、2006年10月12日から15日にかけて金沢大学で開かれた、「ドイツ・日本社会科学会議」で報告しました。
英語で行われた報告です。。この学会は2年に一度、ドイツ、日本で交互に開かれている学会で、ドイツ人、日本双方から社会学者、心理学者が研究報告をし、ドイツと日本の研究者の交流を深めようというものです。言語は英語で行われています。(HPはhttp://www.nichidoku.org/です。)私は13日の午後に報告を行いました。内容は、下記に紹介している東方領土問題に関する研究成果報告書の簡単な概略です。報告に当たって、長めのペーパーと、短めのペーパーを配布しました。ここでは短いヴァージョンを掲載します。長いヴァージョンは、将来出版予定の、この学会の報告をまとめた編著に載せる予定なので、ここには掲載しません。
→報告のペーパー(PDF)
■「国家の檻 −マイケル・マンの国家論に関する若干の考察ー」が法政大学社会学部の紀要『社会志林』(第53巻 第2号、2006)に掲載されました。(2006年9月)
この論文は、マイケル・マンが一連の最近の著作の中で展開している国家論を、主としてヴェーバーの官僚制国家論との対比で論じたものです。マンの「インフラストラクチャー的権力」という概念が、一つのキーワードになりました。なお、この論文は、今年6月の社会学史学会大会での報告を土台にしています。
■『東方領土問題と戦後ドイツのナショナル・アイデンティティ』が、日本学術振興会科学研究費補助金、基盤研究(C)の研究成果報告書として作成され、日本学術振興会に提出されました。(2006年6月)
前回の補助金と加えて、過去5年間の研究の集大成です。しかも、これまでこのテーマでは論文一本しか書いていないので、ほぼ書き下ろしということになります。原稿用紙400字詰め換算で約800枚(A4で231ページ分)の大作です。今年の2月頃から5月にかけて時間の余裕を見つけて集中的に執筆していましたが、博士論文をもう一度書かされたかのような苦労がありました。
テーマは、オーデル=ナイセ線以東の東方領土を、戦後連邦共和国がどのように論じてきたかを中心として、言論分析です。また、ナショナル・アイデンティティ分析の理論的枠組みの開拓も目指しています。いずれ、単著として出版するつもりです。ですが、報告書を読みたいという方にはさしあげます。
なお、このような仕事ができたのも、学術振興会の財政的援助があったからで、事務的な決まり文句としてではなく、謝意を表したいと思います。また、現在は別のテーマ(1999年国籍法改正をめぐる研究)で同機関から補助金をいただいていますが、こちらのテーマでも、きちんとした仕事を完成させたいと思っています。
■富永健一編『理論社会学の可能性 客観主義から主観主義まで』(新曜社、2006))の中に「国民国家の社会理論 −「国家」と「社会」の視点から」という論文が掲載されました。

この論文は、ヴェーバー、戦後アメリカ社会学、1980年代以後の英米社会学において台頭した国家論、そして最近の国民国家論の中からマイケル・マンとアンドレアス・ウィマーの議論などを紹介しつつ、今後の国民国家論の可能性について、社会学理論の知見から考察したものです。国民国家論としては、有名なベネディクト・アンダーソンの「想像の共同体」論、エリック・ホブズボームの「伝統の創造」論、西川長夫の国民国家論など、またゲルナーやスミスのナショナリズム論といった観点から分析されることが多いと思われますが、社会学者の間でもまた独自な分析枠組みが展開されています。こ論文は、そうした社会学者の国民国家論をもう少し知ってもらおうという意図も入っています。全体の論旨は、国民国家を一体的なものとしてとらえるのではなく、「国家」と「社会」という諸制度郡の間で、様々な集合的アクターが活動するプロセスとして
なお、この論文が所収されている富永健一編の編著は、「マクロ」から「ミクロ」まで、「機能主義的」観点から「意味学派的」観点まで(一時代前の標語ですが)、多くの優れた社会学理論家の先生方が執筆されています。全体としてのまとまりはさておき、個々の論文はなかなかどれも読み応えのあるものばかりです。(アマゾンで購入)
■ロジャース・ブルーベイカー『フランスとドイツの国籍とネーション −国籍形成の比較歴史社会学』が2005年10月25日付けで明石書店から刊行されました。定価は税抜きで4500円です。

私と筑波大学の技官をされている佐々木てるさんとの二人でこの本を監訳をしています(共訳者は穐山新さん、石井由香さん、稲葉奈々子さんです)。この本の原タイトルはCitizenship and Nationhood in France and Germanyですが、翻訳書のタイトルには副題もつけました。また、ここには、2000年以後に書かれた、原著にはないドイツに関するブルーベイカーの短い文章も掲載しています。本書の最後には、私が「監訳者解説」を書いているので、関心のある方は読んでください。ブルーベイカーの国籍形成に関する理論的アプローチに関して、およびその現代的意義についての文章です。
この本はフランスとドイツにおける対照的な国籍法(フランスでは出生地主義の比重が高く、ドイツでは純粋血統主義をとる)の形成過程を、それぞれのナショナル・アイデンティティ(「ネーション」の自己理解)との関係から分析するというものです。原著は1992年に出版されたもので、分析の範囲は1990年代初めで終わっています。後に両国とも国籍法が改定され、特にドイツでは大幅な改定がなされました(2000年から改定国籍法が施行れている)。その意味で、この本はもはや「アップ・トゥー・デート」ではありません。しかしこの本の本領は、18世紀末以後の、国籍形成過程の歴史分析にあるので、現在でも翻訳する意味は十分にあると考えています。また、この本は国籍それ自体を分析対象とした研究という点で、現在では古典的地位を占めているといえます。この本の後、類似の問題意識による著作、論文が多く出されました。(アマゾンで購入)
■戦後ドイツの「もう一つの過去」 −東方領土問題とナショナル・アイデンティティをめぐって−
−2004年10月5日 戦後思想研究会(法政大学社会学部教員有志でやっている小さい研究会です)での口頭報告 社会学部棟8階A会議室
第二次大戦でドイツが喪失した東方領土がいかに認識されてきたのか。それがナショナル・アイデンティティとどのような関係にあるのか、それが領土喪失に伴って発生したドイツ人の大量強制移住(「追放」)の記憶とどのような関係にあるのかなど、私の最近の研究テーマを報告したものです。1970年までについてはすでに論文にしていますが、それ以後のことに関しては、今回初めて報告しました。
・内容の簡単の紹介(PDFファイル)(事前のアナウンス用に執筆したものです)
・当日の配布レジュメ(PDFファイル)(同時に大量の資料を配布しましたが、それはここでは省略します)
■社会学とその時代の〈危機〉 −「〈危機の時代〉の行為理論」へのコメントを2004年10月24日におこなわれたシュッツ=パーソンズ研究会で行いました(慶応大学三田キャンパス)
社会科学基礎論研究会が毎年出しているすばらしい(装丁も含めて)理論社会学系雑誌『社会科学基礎論研究』第3号(2004)に掲載された、油井清光、佐藤嘉一、浜日出夫三氏の論文へのコメントです。コメントではありますが、かなり長い論文調のものになりました。なお、この研究会は、社会科学基礎論研究会とかなりメンバーがダブっているもので、主として行為理論=ミクロ理論系の社会学者が中心に運営しているものです。今回初めて出席させてもらいましたが、大変場内温度の高い(熱い)研究会でした。
・配布資料(PDFファイル)
(番外・・・)ジェフリー・アレクサンダー『社会学の理論論法』を翻訳し、青木書店から出す予定です。
かなり前から決まっている予定なのですが、まだ実現していません。共訳者は盛岡大学の鈴木健之さんです。アレクサンダーは、いわゆる「ネオ機能主義」を掲げて1980年代に登場した理論社会学者で、パーソンズ理論の影響を大きく受けた人でした。しかしこの本は、「ネオ機能主義以前」の著作で、パーソンズで言うと『社会的行為の構造』にあたります。マルクス、デュルケーム、ヴェーバー、パーソンズの四人の業績を、社会学理論という視点からとりあげ、「多次元的総合」という観点から各人の理論を批判・分析していきます。
現在、アレクサンダーは、「ネオ機能主義は終わった」と宣言し、新たな「文化社会学」の領域へと展開しています。特に最近の「文化的トラウマ」研究は、現在の「歴史の記憶」問題とも重なり合って、なかなか興味深いものです。今年(2005年)には、上智大学の招聘で来日し、一度だけ講演を行いました。そこで彼が取り上げたのは、中国における南京大虐殺の記憶の問題でした。。
>>旅行記<<
■ポーランド/ドイツ紀行
少し前になりますが、2004年夏(8月23日から9月15日まで)にポーランドとドイツを訪問しました。前半半分はポーランド、後半半分はドイツ。ドイツではベルリンの州立図書館での資料収集で、最近頻繁に通い、資料収集をしている場所です。前半のポーランドは初めての訪問でした。「これが『仕事』か」といわれそうですが、科研費を使って出張としていったものです。しかもそれなりの成果がありました。
今回のポーランド旅行は、旧ドイツ領であるシュレージエンを中心にまわりました。この土地にかつてのドイツ領だだった時代の痕跡はどれほどのこっているのか、戦後の「ポーランド化」がどれほど徹底して行われたのか、ポーランドではドイツとの関係(特に被追放者たちの財産権要求問題がどのようにとらえられているのか)などを自分の目で見てみたいというのが目的でした。 ⇒紀行アルバム