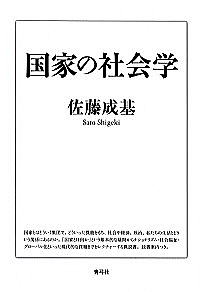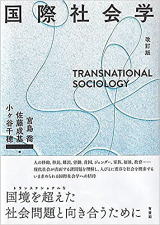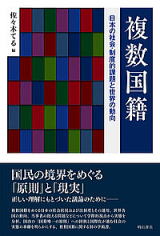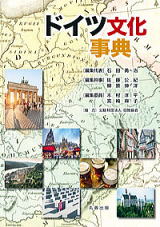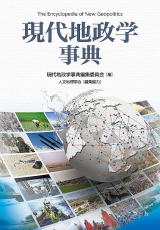最近の仕事から・・・
最近フォーマル、インフォーマルな形で発表・報告したものを紹介します(配布資料がリンクされています)。
■2025年11月30日に早稲田大学国際会議場で開かれた法哲学会2025年学術大会「移民難民問題と法哲学」で「総括討論者」として報告しました。
移民難民の受け入れをめぐる「正義」についての大会です。現代的にも極めて重要なテーマについての法哲学会での学術大会で、2人の総括討論者の1人として「移民難民と国家」というタイトルで報告しました。責任者は静岡大学の横濱竜也さんで、報告は浦山聖子さん(成城大学)、大西楠テアさん(東京大学)、柄谷利恵子さん(関西大学)、宮井健志さん(国立人口問題研究所)、石山文彦さん(中央大学)の5人、もう一人の総括討論者は瀧川裕英さん(東京大学)という顔ぶれでした。1年半前に声をかけていただき、それから時間をかけて準備をし、当日も朝9時半から夕方5時半までという長丁場でした。とても充実した内容でした。法哲学では「正義」に関する価値判断それ自体がテーマになるわけですが、事実がどうなっているのかという関心から出発する社会学とは異和もあります。日頃正面から考えていない問題に直面し、「社会学理論」をやってきた私にとっては貴重な経験となりました。
■2025年11月16日に同志社大学で開かれたドイツ現代史学会例会で「拙著「国民とは誰のことか』(花伝社、2024年)をめぐって」を報告しました。
拙著『国民とは誰のことか』の合評会を開いていただきました。高橋秀寿(立命館大学)にオーガナイズしていだきました。合評会はスイス史研究者の穐山洋子さん(同志社大学)、ポーランド史研究者の福元健之さん(京都大学)のお二人で、ドイツ隣国の観点からコメントいただきました。社会学と歴史学の中間の位置で研究している私(特にこの本の場合は)にとって大変貴重な経験となりました。例会の後半はディーター・ランゲヴィーシェの邦訳書『統一国家なき国民』をめぐり、訳者の飯田芳弘さんもまじえた書評会も開かれました。
■2025年4月19日に神田外語学院で開かれた東欧史研究会2025年度大会「ナショナル・インディファレンスとジェンダー」で、コメンテーターとして登壇しました。
2023年に、マールティン・ヴァン=ヒンダーアハター/ジョン・フォックス編『ナショナリズムとナショナル・インディファレンス』がミネルヴァ書房から翻訳・出版されましたが、こその翻訳者のお1人である中辻柚球さんが中心となって企画されたシンポジウムでのコメンテーターをつとめました。「ナショナル・インディファレンス」の概念は、アメリカの中東欧史学者タラ・ザーラが提唱した概念で、この概念を用いてナショナリズムを以下に分析できるのかを問うのがこのシンポジウムで、「ジェンダー」との関連からその可能性を考えるというものでした。登壇者に関しては、こちらをご覧ください。私は「ナショナル・インディファレンス」概念の意義とその有効性(および限界)について理論的な観点からコメントしました。その内容は次号の『東欧史研究』に載る予定です。いつものことではありますが、分野が異なる歴史学の方々との交流は、私にはとても良い刺激になります。と同時に、社会学界でナショナリズムがあまり大きなテーマにならないことに、若干の寂しさも感じるところです。
■2025年2月1日発行の集英社のPR誌『青春と読書』に、中野剛志著『政策の哲学』(集英社、2025年1月刊)の書評を掲載しました。
中野剛志さんは現役の経済産業省の官僚ですが、評論家としても多数の著作を出している人です。エディンバラ大学で博士号を取得し、経済ナショナリズムに関する英語論文も数本書いていて、学術的な研究者としても十分に通用する高い能力を持った方であると認識しています。今回の新著はロイ・バスカーの科学哲学と歴史社会学的国民国家論とを結びつけ、それを「政策の哲学」と発展させたもので、アカデミック畑の研究者にはなかなかできない大胆な試みです。
書評は短いものですが、こちらからウェッブ上で読めます。
■2024年6月22日の第63回日本社会学史学会一般研究報告の部で、「ハーバーマスと欧州統合 ―トランスナショナルな連帯形成の可能性をめぐって―」というタイトルで報告しました。
生まれて初めてハーバーマスについての学会報告をしました(プログラムはこちら)。ハーバーマスは昨年の9月ころから集中して調べるようになりました。現代ドイツを語る上では触れないわけにはいかない「公共知識人」であり、私自身、移民統合に関する論文や先日の国籍法の本でも、何度かハーバーマスに言及してきました。今回の報告は、欧州統合という1990年代以後のハーバーマスの中心的テーマをちりあげています。ドイツに根付いた、いかにも「ドイツ的」な知識人であるハーバーマスと、アカデミックな社会理論家・哲学者としてのハーバーマスとを連関させる視点を出せるかどうかが課題の一つです。
また、社会学史学会で報告するのは本当にし久しぶり(前回報告したのは15年以上前だったと思います)でした。これからは学史研究をもう少し積極的にやっていきたいと思っています。
なお、2022年から3年間、私が「研究担当理事」としてかかわってきた大会シンポジウム「学説史を通じて「社会学」を問う」は、今年で終了しました。
■2023年11月25日に、単著『国民とは誰のことか ―ドイツ近現代における国籍法の形成と展開』(花伝社)を上梓しました。
久しぶりの単著になります。19世紀初頭のナポレオンの時代にドイツ圏の諸邦において国籍の法制化が始まってから、現代の国籍法をめぐる問題に至るまで、ドイツにおける国籍法の形成とその後の変遷を歴史的にたどり、それを歴史社会学的な視点(といっても何か明確な枠組みがあるわけではないのですが)から考察したものです。私の主要な関心であるネーションと/ナショナリズムに関する研究の一端でもあります。そのため、特に「ネーション」の理解のされ方国籍法と国籍政策との関連に注意が向けられています。
最近は日本でも国籍に関する関心が少しづつ高かまっているということもあり、学術書ではありますが、なるべく一般の読にもわかりやすいように書いたつもりです。国籍法や国籍政策に関する複雑な細部の議論、「社会学的」なネーションに関する議論を展開しつつ、ドイツの国籍に関する一般向けの概説書にもするということで、それぞれのバランスをどうとるかに苦労しました。それに成功しているかどうかは、読者の判断にお任せするしかありませんが。
こちらから購入できます。

■2023年10月17日刊行の北田暁大・筒井淳也編『岩波講座 社会学 第1巻 理論・方法』に「国家の正当性と象徴暴力 ブルデューの国家論からみる国家とナショナリズム」を掲載しました。
『国家の社会学』で論じた「国家と正当性」について、さらに拡張して論じたものです。ブルデューの国家論を社会学の国家研究の流れの中に位置づけながら、その意義と限界、さらに、国家を論じる際に決して忘れることのできないナショナリズムとの関係性について考察しました。「理論・方法」のなかにおさめられた論文の中で、このような学説史的なスタイルで書いたものはないのではないでしょうか。おそらく、「旧世代」の論じ方でしょう。社会学の「理論」の論じ方も、随分と変わったものです。
本は今年から刊行が始まった、13巻からなる『岩波講座 社会学』の第1巻です。こちらから購入できます。

■2023年6月25日に発行された『社会学史学研究』(日本社会学史学会)第45号に「学説史を通じて「社会学」を問う —大会シンポジウムによせて―」を掲載しました。
2022年から日本社会学史学会の研究担当理事の1人になってますが、この文章は昨年の大会シンポジウムの「趣旨説明」です。昨年、今年、来年の3回にわたり「学説史を通じて「社会学」を問う」を共通テーマにしています。昨年はデュルケム、シカゴ学派、ヴェーバをとりあげました。
■2023年4月6日に『国際社会学[改訂版]』(有斐閣)が刊行されました。
2015年に刊行された宮島喬先生、小ヶ谷千穂先生と共編であるこの本の改訂版です。新学期に間に合わせるという予定で、どうにかその通りにできました。
初版がでてから7年がたち、欧州の「難民危機」、日本での入管法改定、コロナ禍などがあり、国際社会をめぐる状況はかなり変化しました。それらを取り込んで、各章ともある程度改変されています。また難民問題に関する新たな章も追加しました。私の担当部分である1章は、かなり書き換えました。また、コラムにある「グローバリゼーション』の説明は全面的に書き換えています。装丁も全く新しくなりました。あと6~7年間大学などでのテキストとして使われることを願っています。
残念ながら、時節柄低下を上げなければなりませんでした。税込みで3千円をちょっとだけ超えますが、生協などで割り引いてもらえれば、どうにか2千円台にのります。
こちらから購入できます。
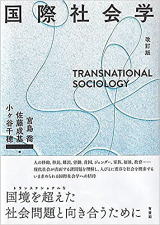
■2023年1月20日に『社会学の力〔改訂版〕』(有斐閣)が刊行されました。
学生向きの社会学用語集の定番となった本書の改訂版が出ました。2017年の初版以来、すでに何度か再版が出ていましたが、今回は新たにいくつかの概念を加えたものになっています。装丁も渋い黄色から薄い青緑に変わっています。私は「パターン変数図式」と「構造と機能」の二つの項目を書いていますが、「構造と機能』の方は多少の修正を加えました。私としては、旧版を持っている方も、あらたに買いなおしていただきたいと思っています。(こちらから)

■2022年12月25日発売の佐々木てる編『複数国籍 日本の社会・制度的課題と世界の動向』(明石書店)に「ドイツの複数国籍――「現実」と「原則」の乖離」を寄稿しています。
コロナ前の2017年から2019年にかけて科研費で行った共同研究の成果です。複数国籍についての学術的な研究としては、最初のものではないでしょうか。私の論文は内容的には2020年にまとめられた科研費の成果報告書に載せた文章をいくぶんか修正・拡張したものです。ドイツにおける複数国籍問題の歴史と現状を概観したものとし、ドイツ語のものを含めてもおそらく他に類似したものはないと思います。近年論じられるようになった「世代限定」モデルの意義や、そもそも複数国籍を今後どう考えていけばよいのかについても、最後の少し触れています(全然十分ではありませんが)。
世界のパスポートの表紙の色を並べたところをイメージしている表紙のデザインが、なかなか気が利いています。こちらから購入できます。
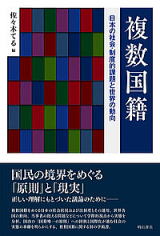
■2022年刊行の『社会志林』第69巻,第3号に「ヴァイマル共和政期のドイツの国籍―国籍の「エスニック化」とその限界」を掲載しました。
ドイツ国籍の歴史シリーズの第2弾です。とはいえ、この論文は学術論文としての筋道だった構成になってはいません。この時期について調べたことを並べた研究ノートのようなスタイルになっています。論旨の中心は、帝政期1913年に成立した帝国籍・国家籍の法をもって「エスノ文化的」な国籍法ととらえる(純然血統原理が用いられていたから)ととらえるこれまでの通説を相対化し、国籍の「エスノ文化」化がヴァイマル共和政期に進んだこと、それがナチス時代の国籍政策への橋渡しになったことをにあります。論文はこちらから閲覧できます。
■2022年10月22日(土)、明治学院大学白金校舎で行われた「移民のシティズンシップ変容と受け入れ社会への影響に関する日仏独共同研究」の研究会で「ドイツの複数国籍をめぐる政治 ―国籍のリベラル化とそれへの抵抗―」を報告しました。
駒澤大学の中野裕二さんが主宰する科研費の研究会での報告です。参加者は中野さんのほか、科研費の共同研究に参加されている3名で、私がゲストとして呼ばれました。少人数ですが、フランスとドイツをフィールドとする方々で、とても中身の濃い議論ができました。内容は佐々木てるさんの主催する複数国籍研究の共同研究の成果によるもので、近々出版される共著本のなかに寄稿している論文をベースにしています。
■2022年5月8日(日)、西日本社会学会第80回大会2日目のシンポジウム「行為論再考 ―経験的実証研究と社会学理論との新たな対話を求めて」で討論者の1人をつとめました。(主催校は神戸学院大学でしたが、全面zoomでの開催でした)
中村文哉さんと鈴木健之さん編の『行為論からみる社会学』の出版を受け、西日本社会学会でこういうタイトルでのシンポジウムを開いていただきました。全体のコーディネーターで、基調講演を担当したのが中村さんです。その他に山田富秋さん(松山大学)、井腰圭介さん(帝京科学大学)、石橋潔さん(久留米大学)が報告をされました。討論者は熊本大学の多田光宏さんと私です。司会は広島大学の江頭大蔵さんでした。(報告タイトルなど詳しいことはこちら。)
若い世代で経験的実証研究は深めれている都に対し、理論研究は近年退潮気味にあります。そのようななか、「行為論」という切り口から社会学理論の可能性を、特に経験的研究にとって社会学理論がどのような役割を果たしうるのかという、とても古典的な問題を掘り下げたもので、なかなか充実したものになりました。私は西日本社会学会の学会員ではありませんでしたが、大変に良い機会を与えていただきました。
■2022年4月に発行された現代史研究会の雑誌『現代史研究』67巻に蘭信三・川喜田敦子・松浦雄介編『引揚・追放・残留 戦後国際民族移動の比較研究』(名古屋大学出版会,2019年)の書評が掲載されました。
この書評が対象にしている『引揚・追放・残留』は戦争や脱植民地化に伴う強制的人口移動の比較を行った論文集です。これまであまり扱われてこなかったこの種の「移住」現象の研究として先駆的なものになるでしょう。編者の蘭氏、川喜田氏はすでにこの領域で業績のある方です。分量は1万字ほど(原稿用紙換算で25枚程度)で、書評としてはかなり長いものです。社会学系の雑誌とは異なり、歴史学の業界では一般に書評の分量が多い傾向があります。
■2022年3月25日に刊行された日本大学社会学会の会誌『社会学論叢』No.202に「タルコット・パーソンズのモダニティ論 ―「パターン変数」図式を手掛かりに―」を掲載しました。
昨年7月に日大社会学会で同タイトルの報告したものを文章化したものです。私としては、本当に久しぶりのパーソンズパーソンズに関する論文です(18年ぶり?)。とはいえ、その土台は2017年に出版された入門用の本『社会学の力』に書いた「パターン変数図式」にあります。この短い文章で説明した「パターン変数図式」を用いて、パーソンズ理論の全貌を「モダニティ論」として再解釈するというのが、この論文の主旨です。また、そこでドイツの社会学者レックヴィッツの最近の後期近代論における「組織化された近代」概念を手がかりにしています。
なお、この号は7月の大会で報告された犬飼裕一さん、久保田裕之さん(どちらも日大の教員)の論文も掲載されています。どちらも「近代」をテーマにしていて、まったく異なった観点からのモダニティ論が展開されていて、大変読み応えのあるものになっています。

■2022年3月に発行された『社会志林』第68巻、4号に「ドイツ最初の国籍法の成立過程(2) ―ドイツ国籍法と「エスニック」なネーション概念との関係を再考する―」を掲載しました。
第68巻、3号に載せた(1)の後半部分です。1848年革命の憲法制定をめぐる国民議会での「ドイツ人」をめぐる論争と1870年の北ドイツ連邦国籍法の制定過程について分析しています。最後に1871年に建国されたドイツ帝国の国籍についても、簡単にふれています。論文はこちらから閲覧できます。
■2022年2月21日に東京愛宕にある公益社団法人、自由人権協会の外国人の人権小委員会の勉強会で「ドイツ国籍法と「エスニック」なネーション概念 ―血統原理と民族帰属概念を中心に―」という」を報告しました。
殷勇基弁護士から、ドイツの国籍法について話してもらいたいという依頼を受けてこの報告をしました。現在取り組んでいるドイツ国籍法の歴史の研究から「民族帰属」概念を中心に話をまとめました。勉強会は協会の事務所からzoomを通して行い、事務所には私を含めて5人、zoomでの参加者は20名強という具合でした。討論では、日本の国籍法との比較を中心に議論がなされました。
■2021年12月に発行された『社会志林』第68巻、第3号に「ドイツ最初の国籍法の成立過程(1) —ドイツの国籍法と「エスニック」なネーション概念との関係を再考する―」を掲載しました。
12月12日の移民政策学会冬季大会(下記)で報告した内容の前半を詳しく論じたものです。3月に発行予定の第68巻、第4号に後半部分を掲載する予定です。全体を合わせて、ナポレオン時代(1810年前後)から1870年の北ドイツ連邦の「連邦籍および国家籍の取得と喪失に関する法律」制定にいたるまでの過程を分析し、そこでどのような「関心」が働いていたのかを考察しています。今回の前半部分は、最初の序論的考察に加え、18世紀の「領域国家」の時代から1851年のゴータ条約までのドイツ諸邦の国籍法制の形成について扱っています。それに対し、後半は1848/49年のドイツ革命と1867年北ドイツ連邦成立から1870年のの北ドイツ連邦の国籍法成立を扱い、1871年ドイツ帝国成立後の国籍政策についても少しだけ触れる予定です。19世紀ドイツの資料は意外にデジタル化が進んでいて、現在のコロナ禍においてもかなりの資料にアクセスすることができました(それに対し、第一次大戦後になると、とたんにアクセスが難しくなります。著作権の関係でしょうか)。論文はこちらから閲覧できます。
■2021年12月24日に岩波書店から公刊される、「シリーズ戦争と社会」の第1巻、『「戦争と社会」という問い』に、「戦争と国家 —総力戦が生んだ強力でリベラルな国民国家」が掲載されました。
今年から始まった岩波のこのシリーズの第1巻に「戦争と国家」というテーマで書いてほしいという依頼を受け、拙著『国家の社会学』で十分に論じきれなかったテーマとして20世紀の総力戦と先進諸国の国民国家形成との関連を論じてみました。『国家の社会学』を補完するような内容になっています。今回の論文では、英米仏独と並んで日本も比較の対象の一つとして取り入れています。他国の考察が、基本的に二次文献(既存の研究)を参照しているのに対し、日本に関してはだいぶ一次データも用いました。総力戦というと故山之内靖さんの「総力戦体制」論がよく知られていますが、総力戦の結果と「総力戦体制」を同質的に結びつけてしまう山之内さんの議論に対する批判という意味も込めています(そのことについて、論文の中では触れられませんでしたが)。こちらが出版社の紹介サイトです。こちらから購入できます。

■2021年12月12日(土)にzoomにて開催された冬季移民政策学会大会、自由報告部会にてで「ドイツ最初の国籍法の成立過程 ―「エスニック・ネーション」化する以前のドイツの国籍法—」を報告しました。
半年ほどまえから始めた、1870年のドイツ国籍法制定に至る過についてのプロジェクトの最初の成果報告でした。既存研究の知見と、自ら収集した19世紀の資料を用いたものです。国籍法を「ネーション」(「ナショナルな自己理解」)と関連付けて理解するブルーベイカーの枠組みが、ここでは必ずしも通用しないこと、ドイツの諸邦よび北ドイツ連邦の国籍法に関しては、国家の統治上の実務的関心が中心的役割を担っていたことを主張しまた。「ネーションではなく国家」というのがここでのポイントなのですが、そこが曖昧だという指摘も受けました。
この研究は、1871年以後も含め、ドイツの国籍法の歴史に関する包括的研究(パトリック・ヴェイユがフランスでやったことをどいつでやってみようというおこがましい試み)の一環です。この包括的研究の方も、早く終わらせたいところです。
移民政策学会で報告するのは今回が初めて、zoomでの学会発表も今回が初めてでしたが、進行もよく、議論もそれなりに盛り上がりました(学会のプログラムはこちら)。なお、今回の報告の内容は、『社会志林』に2部に分割して公刊する予定です。最初の部はすでに校了しています。
■2021年7月10日(土)に開催された日本大学社会学会大会、午後のシンポジウムで「タルコット・パーソンズのモダニティ論 —「パターン変数」図式を手がかりにして—」を報告しました。
今年101周年となる歴史ある日本大学社会学会での報告です。午後のシンポジウムは「モダニティを再考する」という共通テーマをかかげ、私のほか日大文理学部の犬飼裕一さん、久保田裕之さんがパネリストとして登壇しました。討論者は大黒正伸さん(創価大学)、清水強志(創価大学)のお二人でした。(こちらで当日のプログラムが見られます。)
私がパーソンズにつて公開の場で話をするのはほぼ20年ぶりでした。今回は、私なりのパーソンズ理解をまとめる機会ともなり、とても、議論も活発で、とても有益な場となりました。
■2021年5月に発行された移民政策学会の学会紙『移民政策研究』Vol.13に明石純一著『人の国際移動は管理されうるのか ——移民をめぐる秩序形成とガバナンス構築』(ミネルヴァ書房、2020年)の書評を掲載されました。
明石さんの近刊を書評したものです。人の国際移動の管理をめぐる問題を、経験的調査の結果を踏まえつつ論じた著作で、なかなか読みごたえがありました。
■2021年4月に、レビュー論文 "Modernity, postmodernity, and late modernity: A
review of sociological theories in contemporary Japan" が国際社会学会の雑誌International sociology, volume 36, Issue 2 (March 2021)に掲載されました。
この号は3月号ではありますが、オンラインでは4月、書誌体では5月にようやく公刊されました。ここで「日本の社会学を特集しています。本誌のエドトリアル・ボードのお1人である小熊英二さんが代表してイントロを書き、それに続いて、私のものを含め14本の分野別のレビュー論文が並べられています。英語で日本の社会学の現在を伝える画期的な企画です。
私は「社会学理論」の分野を担当しています。「日本の社会学理論」というくくりで考えたことがなかったので、依頼を受けたときは戸惑いました。結局、「モダニティ」の問題を軸にしながら、社会学理論の分野で充実した実績をもっている人を3人選んでレビューしました。3人とも60歳近い、あるいは60を超えた「大御所」で、近代化論、ポストモダン論、後期近代論の時代を経てきた方々です。この3人の比較検討を通じて、日本の社会学界内の「社会学理論」の現在の位置を確認する試みですが、うまくいっているかどうかはわかりません。(こちらから目次が見れます)

■2021年1月9日、武田里子さんが主宰している「複数国籍学習会」で「ドイツにおける重国籍-「現実」と「原則」の乖離―」というタイトルで報告しました。
この研究会は複数国籍(重国籍)当事者の方々が中心の学習会で、複数国籍や国際結婚について研究する社会学者の武田里子さんが主宰しているもので、今回が14回目ということです。私は、佐々木てるさん代表の科研費の研究課題の成果報告書に掲載した、今回の報告と同名の論文(4項目下の欄で紹介している)と、3月に『社会志林』に掲載した論文で論じられている「国民の自己理解」との関係についての考察を少し加えて、1時間弱の報告をしました。15人ほどの方が参加され、ドイツ人と国際結婚されている方、ドイツ人と日本人のハーフの方なども参加していて、私としてもとても有意義な機会でした。
■2020年10月に出版・刊行された『ドイツ文化事典』(石田勇治ほか編集、丸善出版)で「ドイツの国境問題」の項目を分担しています。
総ページ数744の大型事典です。歴史、政治、食、芸術など多方面の項目が並べられています。私が分担した項目では、17世紀以来のドイツの「国境」に関する歴史を概説しています。高価でから、図書館等で見ていただけるとよいと思います。出版社のサイトはこちらです。
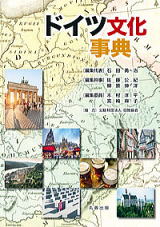
■2020年10月20日に刊行される中村文哉・鈴木健之編『行為理論からみる社会学 -危機の時代への問いかけ』(晃洋書房)に「行為論から見た国家 -ヴェーバー『社会学の根本概念』から国家を考える」を掲載しました。
ヴェーバーの有名な著作『社会学の根本概念』を国家論の視点から読み、ヴェーバーの国家論の限界と可能性とを論じたものです。『国家の社会学』の第2章の内容を深めたものです。
本全体は「行為論」という、社会学のなかではすでに時代遅れとも考えられる視点を前面に出しています。ヴェーバー、シュッツ、ガーフィンケル、ゴッフマン、パーソンズ、ギデンズなどといった社会学理論の中心的人物の議論を論じた論文と、「死」や「国家」を行為論の視点から論じた論文が集められていて、中身はとても充実しています。一見難解な専門書のようなタイトルですが、大学で使うテキストを想定して書いていますので、ぜひ、気軽に手に取っていただきたいと思います。値段(税抜き3200円)は一般書としてみると高いですが、この種のテーマの本としてはかなり努力をしています。(⇒こちらから購入できます)

■2020年7月1日に刊行された雑誌『エトランデュテ』(在日法律家協会会報)第3号に、座談者の1人として参加した座談会「出生地主義の拡大と複数国籍の承認について」の記録が掲載されています。
座談会はコロナ感染が始まる前の1月26日の夜、お茶の水にある明治大学の校舎の一室を借りて行われました。参加者はこの座談会の企画者で、『エトランデュテ』の編集委員の1人であり、当日司会をした柳赫秀さん(神奈川大学教授で国際法が専門)、青森公立大学の佐々木てるさん、早稲田大学の遠藤正敬さん、弁護士の殷勇基さん、そして私の5人でした。外国人労働者の受け入れや移民政策、「多文化共生」などが問題にされ、議論されるようになっている今日の日本において、なぜか国籍に焦点が当たることは少ない。そのようななか、この座談会では「5世(もしかして6世)まで下った外国人子供に居住国日本の国籍が与えられない』日本の現状は、「移民2,3世以下に居住国の国籍が与えられる世界的潮流からほど遠い」のではないか、また「世界的に多くの国々が二重国籍の意味を再認識し積極的に容認する潮流がある現状に目を向けるべきではないか」(柳)という問題関心から、この座談会では出生地主義と複数国籍をテーマにして議論を行いました。佐々木さんは、遠藤さんは国籍を主な研究対象とされていて、それぞれの研究関心の観点から発言され、私はドイツの国籍法との比較という視点から、日本における出生地主義導入の(不)可能性のほか、国籍のもつ歴史的意味についても言及しました。殷さんとは初対面でしたが、弁護士の仕事でお忙しいにもかかわらず学術的な研究にも明るい方で、その学識に感心しました。また、柳さん座談会全体をとてもパワフルにリードされました。全体として中身の濃い津論会で、私としても「言いたいことは言えたな」という実感を得ました。
雑誌は博英社というマイナーな出版社から出されているので、やや手に入りにくいのが残念です。アマゾンではこちらから購入できます。

■2020年3月31日に刊行された科研費の研究成果報告書『重国籍制度および重国籍者に関する学際的研究』(研究代表:佐々木てる)に、「ドイツの重国籍制度 -「現実」と「原則」の乖離-」を寄稿しました。
2017年度から学術振興会科学研究費助成事業の「基盤研究(B)」として研究助成を受けてきた重国籍に関する研究プロジェクトの成果報告書です。研究代表者である佐々木てるさん(青森公立大学)に労をとっていただき、できあがったものです。佐々木さんを含め、研究にかかわった14名の文章が掲載されています。私の報告は、『社会志林』に載せた論文「重国籍に抵抗するドイツ」と大部分重なっています。
■2020年3月に「重国籍に抵抗するドイツ -「国民の自己理解」との関係からみた文化社会学的考察―」を法政大学社会学部学会発行の『社会志林』第66巻第4号にて公刊しました。
ドイツ連邦共和国における重国籍政策の歴史をたどった後、400万人以上の重国籍者がいると想定されながら、いまだに正式に重国籍を容認しないはなぜなのかをドイツの「国民的自己理解」(わかりやすく言い換えるとナショナル・アイデンティティ)との関係に留意しながら分析したものです。ドイツの重国籍政策の歴史を単純にたどった研究は官憲の限りドイツ語でも日本語でもありません。しかしこの論文の重点は理論的な視点にあります。スミスやブルーベイカー以来しばしば使われる「シヴィック/エスニック」という二項図式を批判的に再検討し、「リベラル/コミュニタリアン/エスノ伝統主義/エスノ血統主義」の四項図式に置き換えたほうがうまく説明がいくだろうという議論を展開しています。論文にしてはやや長めですが、政策史的部分と分析的部分が同居していることがその理由です。論文はこちらから読めます(⇒)。
なお、政策史的部分だけをとりあげ、それに若干加筆したものが重国籍研究の科研費成果報告書(佐々木てるさん代表)にも掲載されます。
■2020年2月17日(月)『公明新聞』の読書欄に将基面貴巳著『愛国の構造』(岩波書店、2019年)の書評を寄稿しました。
新聞社から頼まれて初めてこの本を知りました。たしかに「ナショナリズム」の研究は多数ありますが、「愛国主義」を「愛国主義」という言葉で正面からとりあげた研究はほとんどなく、そのアプローチはとても新鮮でした。著者は欧州政治史が専門の方で、欧州北米のみならず日本の「愛国主義」の思想を丹念に検討し、その「構造」を明らかにした名著だと思います。興味のある方はぜひご一読ください。私の書評はこちら(⇒)から読めます。
■2020年1月31日に出版された『現代地政学事典』(丸善出版)の中で「マイノリティ・ナショナリズム」「ナショナリズムと戦争/紛争」の二つの項目を執筆しています。
地理学の研究者が中心になって作成された本格的な「地政学」の事典です。「地政学」という分野は最近注目があつまりつつありますが、その境界はかなり広いようです。社会学を含め、人文社会系のかなり広い分野の研究者・学習者におすすめです。ナショナリズムや国家に関する項目も多く、私の執筆しているのはその一部です。その他、国際政治系の項目もかなり含まれています。こちらから詳細が見れます。購入はこちらから(高額ですが)。
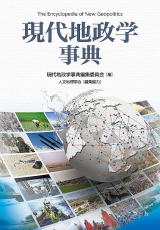
■英国で発行されているナショナリズム研究の代表的学術雑誌Natins and Nationalis, Octiber 2019 (Volume 25, Issue 4)での吉野耕作先生を追悼する特集 "Kosaku Yoshino Symposium"に "The nihonjinron in daily practices: Yoshino's "bottom-up" approach to nationalism"
を寄稿しました。

昨年9月2日に惜しまれつつ他界された吉野耕作先生の追悼特集がNations and Nationalism誌でた。企画されたのは英国で教えていらっしゃる一條都子さんです。私はここで、日常的に「消費」されるナショナリズムという吉野先生のアプローチの意義について強調しました。私は吉野先生と特にお付き合いが長かったというわけではないのですが、何度か研究面で非常にお世話になったことがありました。吉野先生のご研究についてあらためてまとめる貴重な機会をいただきました。
「シンポジウム」には一條さんを含め、私以外5名の方が寄稿されています。目次はこちらからご覧いただけますが、大学の図書館などを通さない限り有料になります。
■2019年9月に刊行された『歴史学研究』(歴史学研究会編』No.987に高橋秀寿著『時間/空間の戦後ドイツ史――いかに「ひとつの国民」が形成されたのか』(ミネルヴァ書房、2018)の書評が掲載されました。
この高橋氏のの近作は、映画、流行歌などの文化現象から戦後西ドイツにおいてどのように「想像」されてきたのかを論じた、大変に興味深い研究です。文化に疎い私にとっては大変に良い勉強にもなりましtあ。
■2019年8月31に、宮島喬先生と私が編者となった『包摂・共生の政治か、排除の政治か――移民・難民と向き合うヨーロッパ』が明石書店から刊行されます。
ヨーロッパにおける右翼排外主義の台頭と、それにも関わらず移民・難民を包摂し、共生の道を探り続けているヨーロッパ諸国の状況を論じた10本の論文から成り立っています。イタリア、オランダ、スウェーデン、チェコなどを扱った論文も収録されています。移民・難民をめぐる最近のヨーロッパ諸国の政治に関心のある方はぜひ手に取っていただきたいです。私はドイツのAfDの台頭を、グローバル化に伴う社会・政治の構造的変化と関連させて論じた論文を寄稿しています。また、宮島先生と共著で、近年のヨーロッパの移民・難民をめぐる政治状況を概観した「序章」も執筆しています。
こちらからご購入ください。

■2019年7月20日、東洋大学白山キャンパスで行われた「「パトリック・ヴェイユ『フランス人とは何か』刊行記念シンポジウム」でコメントを担当しました。
2002年にフランスで出版されたパトリック・ヴェイユの労作の邦訳が『フランス人とは何か 国籍をめぐる包摂と排除のポリティクス』というタイトルで今年の6月に明石書店から出版されました。このシンポジウムはそれを記念して開かれたシンポジウムです。この書は、アンシャンレジーム期から1990年代までのフランスの国籍法や国籍政策の歴史を詳細に論じた見事な研究です。この書が宮島喬先生のほか、大嶋厚さん、中力えりさん、村上一基さんの手で邦訳されました。
シンポジウムでは宮島先生のほか、南山大学の菅原真さん、弁護士の丸山由紀さんがフランスや日本の国籍法についての報告を行い、その後朝日新聞の大野博人さんと私がコメントをしました。私は、ロジャース・ブルーベイカーの国籍に関する「文化的」で「ナショナリスト」的なアプローチを踏まえながら、「国籍と「ネーション」」というタイトルで、ヴェイユに対してやや批判的な観点から話をしました。
会場には思っていたよりも人が集まり、7~80名は参加していたのではないでしょうか。これまで日本では自明視されてあえて論じられることの少なかった国籍についての関心が高まっているらしいことは喜ばしいことだと思います。
■2019年6月2日,慶應義塾大学(三田キャンパス)で行われた「カルチュラル・タイフーン2019」,「「朝鮮戦争」と21世紀のナショナリズム」のセッションで「冷戦下のナショナリズムと国家形成 -朝鮮戦争を切り口にして-」を報告しました。
佛教大学の崔銀姫の発案による学会報告です。「朝鮮戦争」もつ歴史的な重要性をあらためて見直してみようという目標のもと,崔さんとソウル大学の政治学者、南基正,そして私の三人が報告しました。崔さんが「ポスト冷戦と「戦争」言説の変容 -二つの世代が語った『朝鮮戦争』における戦争言説―」,南さんが「朝鮮戦争と日本 ―朝鮮戦争の原体験と戦後日本の自己認識の形成―」という報告でした。私は,崔さんの論じた朝鮮,南さんの論じた日本に加え,ドイツの事例を加えて,三者間の比較の観点を提起しました。
カルチュラル・タイフーンはこれまで全く縁のなかった学会で,関心も全くなかったのですが,崔さんの誘いで今回初めて報告しました。全体として,思ったよりも閑散としていて,我々のセッションの参加者も10名程でしたが,議論は結構盛り上がりました。
■2019年4月22日に刊行される高谷幸編『移民政策とはなにか 日本の現実から考える』(人文書院)に「国籍・シティズンシップ――出生地主義の導入は可能か」を掲載しています。
4月1日から執行された改定入管法に関連して移民政策に関する本がたくさん出版されていますが、本書もその一つです。10章に序章、終章がついていて、労働、教育、社会保障、技能、世論などテーマ別に別の著者が執筆を担当しています。見切り発車できちんとした制度を整えないまま「外国人材」への門戸を開いた今回の入管法改定に対して批判的な視点が共有されています。ただし、私が書いた国籍・シティズンシップの問題は、今回の入管法改定をめぐる論争のなかではあまり注目されていません。ほかの章に比べ、私の章(9章)は少し離れた視点から書かれています。
こちらから購入できます。⇒

■2019年2月17日(日)、東京駅前の立命館東京オフィスで行われた社会運動論研究会で「グローバリズムとナショナリズム――ドイツのための選択肢(AfD)の台頭と新たな政治的対立軸」を報告しました。
これまで全く縁のなかった「社会運動論研究会」から報告を依頼されました。排外主義や「右翼」の政治運動が「社会運動」の枠組みのなかで論じられる機会が増え(それは今の時代を反映してのことでしょう)、それが私のドイツにおける排外主義や右翼ポピュリズムの研究に関心を寄せいていただいた理由でしょう。報告は、今編集中の本(今年度中には出版したいのですが)『包摂・共生の政治、排除の政治』(仮題)のために書いたばかりの原稿をベースにしています。「グローバリズムとナショナリズム」を新たな政治的対立の軸ととらえるという私の現時点での仮説について論じました。私に声をかけていただいた樋口直人さんをはじめ参加者の方々とかなり突っ込んだ充実した討論ができました。
■2018年12月1日、立教大学池袋キャンパスで開かれた、東欧史研究会主催のシンポジウム「歴史としての「ユーゴスラヴィア」――建国100年の地点から振り返る」にコメンテーターとして登壇しました。
第一次世界大戦が1918年に集結してから百年目にあたる今年は、様々な「100年」が追想されていますが、すでに消滅した国家「ユーゴスラヴィア」も建国から百年目に当たります。東欧志研究者の若手を中心に、ユーゴスラヴィア建国百年を振り返るシンポジウムが開かれ、地域でも学問分野的にも「門外漢」の私がコメンテーターを頼まれました。私の役割は、ユーゴスラヴィアの民族問題の歴史学的研究に、ナショナリズム研究の観点からコメントを加えるというものだったと認識し、できるだけその観点に沿ってコメントしたつもりでしたが、それに拘りすぎて歴史学者が中心の研究会ではやや説得力を欠いたていた感じもありました。しかし、研究会それ自体は大変な盛況で、100人近い参加者があったのではないでしょうか。最近の日本社会学会大会最終日のシンポよりもはるかに活気があったように思います。ユーゴスラヴィア現代史研究の大家である柴宜弘先生やハプスブルク史研究大家である大津留厚先生ももディスカサントとして参加され、ソ連史研究の大家でナショナリズム研究者として有名な塩川伸明先生も出席されていました。
こちらがシンポジウムのチラシです。
■2018年10月15日、静岡県立大学大学院国際関係学研究科附属グローバル・スタディーズ研究センター主催の公開シンポジウム「逆流するグローバリゼーションにゆれる市民権」第1回ミニシンポジウムにて、「「ドイツ人」とは誰なのか -「国民」の基準をめぐる争い-」を報告しました。
1日に予定されていたシンポジウムでしたが台風で延期になりました。当初の予定では関西大学の柄谷利恵子さんが報告を行う予定でしたが、日程の調整ができずに欠席されました。そのため報告は私のほかに立命館大学の南川文里さんの2名になりました。シンポジウムは授業の一環で行われたので、教室には受講されている学生さんがぎっしりと座っていました。報告の後、場所を移して質疑応答が行われました。なかなか活発な議論が行われました。(⇒)
私の報告は国政法改定以後の帰化政策を中心にとりあげ、「国民」の基準が明確化されていった経緯を話しました。
■2018年10月13日、講談社のネットメディア『現代ビジネス』に「ドイツ右傾化勢力が敵視する〈68年世代〉リベラルとは何か」が公開されました。
学術論文ではなかなか書けなかったけるども、会話のなかではよく話題にしていたドイツの「68年世代」と右翼の関係についてあらためて見つめなおし、論じてみました。現代ビジネスの編集者の方と話し合いをしているとき、いい機会なのでまとめてみようと思いつきました。68年からちょうど50周年にあたることしは、ハインツ・ブーデやアルミン・ナセー(ナセヒ)といった著名な社会学者が「68年」について本を出していますが、それらの本も簡単に言及できました。ただ、学術論文ではないので、参照文献は示されていません。
私の小文はこちらからご覧いただけます(⇒)。
■2018年9月に刊行された『社会志林』(法政大学社会学部学会)第65巻第2号に「グローバル化のなかの右翼ポピュリズム -ドイツAfDの事例を中心に」が掲載されました。
今年4月の「国家論研究会」で報告したペーパーを加筆修正したものです。ミネルヴァ書房の『排外主義の国際比較』に掲載したものが、ほぼ2016年時点で書かれたものであるのに対し、こちらのほうはより最近の情報を入れています。しかしAfDを中心にしています。また、この論文の課題は、欧州全体の右翼ポピュリズムを把握する分析の枠組みを提示した理論的な論文でもあります。従来の「左右」の対立図式が右翼ポピュリズムを十分にとらえられないことを主張しています。
こちらから論文が閲覧できます。
■2018年9月15日、甲南大学で開かれた2008年度日本社会学会大会一般報告にて「重国籍制度の国際比較(3)-ドイツにおける重国籍容認への抵抗」を報告しました。
青森公立大学の佐々木てるさんが代表になっている科研費での研究プロジェクトの成果報告です。5人の報告者が一つの部会を独占するかたちになりました。議論も盛り上がりました。
■2018年9月に発行された樽本英樹編著『排外主義の国際比較―先進諸国における外国人移民の実態』(ミネルヴァ書房)に「なぜ「イスラム化」に反対するのか―ドイツにおける排外主義の論理と心理」を寄稿しました。
フランス、イギリス、ドイツ、イタリア、アメリカ、北欧諸国、日本、韓国における排外主義をめぐる政治を分析した論文を集めたものです。私はドイツについて書きました。初稿は約2年前のものなので、あまり最近の動向には触れられていませんが、ペギーダやAfDに参加したり支持したりする人々の「排外主義」への動機づけの論理と心理を、できるかぎり当事者の視点に立って解明しよと試みたものです。(こちらから購入してください。)

■2018年6月24日、山梨大学で開かれた日本社会学史学会大会二日目に行われたシンポジウム「グローバル化と各国社会学理論の新潮流――アメリカ社会学理論――」において、「討論者」として登壇しました。
シンポジウムでの報告は「Alexander社会理論の現在―文化社会学からの市民社会論の展開―」(兼子愉氏)、「否定的評価と自己に関するこれまでと今後―内面化からの抵抗へ、そして抵抗の困難へ」(井口尚樹氏)、「マイケル・マンの理論枠組とその拡張可能性」(上田耕介氏)、討論者は小谷敏氏と私でした。最近ほとんど顧みられることのなくなったアメリカの社会学理論について、あらためて光を当てた企画でした。アレクサンダーの文化社会学もマンの歴史社会学も、決して「新潮流」ではなく、最近20~30年くらい間の大きな流れです。私は、三つの報告にあらわれている「アメリカ社会学らしさ」、その特徴的な理論的道具立てないし問題設定について指摘しました。
なお、大会についてはこちらをご覧ください。
■2018年6月3日(日)に法政大学市ヶ谷キャンパスボアソナードタワー25階会議室Cで行われた「重国籍制度および重国籍者に関する学際的研究」の研究会で「ドイツにおける重国籍――政策、実情、およびその容認への抵抗」を報告しました。
青森公立大学の佐々木てるさんを代表者とする科研費基盤Bによって行われている研究会での報告です。私もこの研究の「分担者」として参加しています。ドイツではよく知られているように、1999年の国籍法改定において出生地主義を導入し、それまでの純然血統主義の国籍制度から脱することになりました。しかし、その法改定の時以来、政治論争の中心的なテーマになっていたのは出生地主義ではなく重国籍の方だったのです。現在に至るまで、重国籍を容認するか否かは政治的テーマの一つになっています。ドイツでなぜ、いかに重国籍が問題にされているのかを、「文化社会学」的視座から考察したのが、この報告です。その前提として、これまでの政策の変遷と重国籍者の数量的な実情についても簡単にふれました。
■2018年4月29日(日)に法政大学市ヶ谷キャンパス大学院棟301教室で開かれた国家論研究会において、「グローバル化のなかの右翼ポピュリズム ―ドイツAfDの事例を中心にして」を報告しました。
2015年度から3年間支給された科研費を用いた研究成果の一部としての報告です。科研費のタイトルにしていたのは「排外主義」だったのですが、事実上、3年間AfDという右翼ポピュリスト政党の動向を追うことに終始しました。しかしこの報告では、単にAfDの動向にとどまらず、欧州の右翼ポピュリスト政党を理解するための枠組みの構築を目指しています。同時に、昨年から今年にかけてドイツで立て続けに公表されているAfD支持者についての調査研究の成果もできるかぎり盛り込んでいます。
この報告は近々論文として発表する予定です。
■2018年4月に刊行された『大原社会問題研究所雑誌』714号に新倉貴仁著『「能率」の共同体 ――近代日本のミドルクラスとナショナリズム』の書評が掲載されました。
非常にユニークな日本のナショナリズム研究である新倉貴仁氏の近著を書評しました。書評としてはかなり長いものです。近代日本の社会経済的な変動との関連から明らかにしたものです。「「文化」のナショナリズム」という概念がキーになります。(⇒閲覧可)
■2018年1月に刊行された『立命館言語文化研究』29巻3号に「ドイツ人の「追放」、日本人の「引揚げ」 --その戦後における語られ方をめぐって――」が掲載されました。
約1年前に立命館大学で開かれた朴裕河さんの著作『引揚げ文学論序説』をめぐるシンポジウムでの報告を論文にしたものです。
■2018年3月に刊行されたInternational Journal of Japanese Sociology, vol.27 (2018)にAkiko Hashimoto, The Long Defeat: Cultural Trauma, Memory, and Identity in Japan (Oxford: Oxford University Press, 2015)の書評が掲載されました。
日本の敗戦の記憶について分析したアキコ・ハシモトさんの著作を書評しました。にほんでは盛んに論じられるテーマですが、公の政治の場での語りではなく、家族内での会話やポピュラー・カルチャー(歴史漫画など)を題材にした本格的な社会学的研究です。比較の視点もあり、日本の平和主義的な記憶の文化を、ドイツのものと比較して特徴づけるところなどは、とても興味深いものです。全体としてバランスが取れていて、好感が持てます。無料公開はされていませんが、こちらから読めます⇒。
なお、この本は、私がこの書評を書いている翻訳が刊行されました。橋本明子(山本由美訳(『日本の長い戦後:敗戦の記憶・トラウマはどう語り継がれているか』(みすず書房)です。
■2017年8月31日に『国家の社会学』(青弓社)の増刷ができあがりました。
2014年末に出版されたものです。2年半以上がたちますが、ようやく増刷を出していただきました。国家についての社会学的な概説として、なかなか他に類書がないものだと自負しております。講義やゼミのテキストそて用いていただけるとありがたいです。今後とも、よろしくお願いします。
■2017年7月に刊行された『社会学理論応用事典』(丸善出版)に「カルチュラル・ソシオロジー」「社会構造と社会変動」を分担執筆しました。

社会学の理論と概念をまとめた大型の事典です。価格が2万円を超えるので、個人で購買するのはなかなかきついですが、、体系的でよくできています。図書館などで使っていただけるとよいかとおもいます。(⇒購入)
■2017年7月発行の『社会志林』第64巻、第1号に「カテゴリーとしての人種、エスニシティ、ネーション -ロジャース・ブルーベイカーの認知的アプローチについて-」が掲載されました。
昨年10月に出版されたブルーベイカーの翻訳『グローバル化する世界と「帰属の政治」 -移民・シティズンシップ・エスニシティ―』の編訳者解説の第3節を詳しくしたものです。また、昨年の日本社会学会大会で報告した時の議論も参考になっています。ブルーベイカーの「認知的視座」を、1990年代の彼の業績の流れの中に位置づけつつ、その内容と社会学的分析にとっての有効性などについて論じています。(⇒こちらから閲覧できます)
■2017年6月10日刊行の友枝敏雄・浜日出夫・山田真茂留編『社会学の力 最重要概念・命題集』(有斐閣)に「パターン変数図式」「構造と機能」の二項目を寄稿しました。

これはとても良い本です。「新しさ」や「わかりやすさ」にこだわって変に奇をてらったようなところがない、極めてオーソドックスな社会学の概念・命題集です。こういう社会学のスタンダードな教科書が、なぜか日本には少ないのが実情です。「これが、社会学です」というコピーも効いています。装丁は、有斐閣にしては珍しく単色(しかも暗めの黄色)で渋いです。個人的には気に入っています。
私が寄稿した二項目はどれもパーソンズに関連したテーマでした。パーソンズは私の卒論・修論であつかった社会学理論家で、今はそこから離れてはいますが、この項目を担当する人が他にあまり見つからなかったのでしょうか、編者から依頼されました。
社会学の「スタンダード」を学びたい人には、ぜひ手に取ってもらいたい本です。(⇒こちらから購入できます。)
■2017年5月30日に大学院博士課程の諸君と編集・翻訳したロジャース・ブルーベイカー『グローバル化する世界と「帰属の政治」 移民・シティズンシップ・国民国家』(明石書店、2016年)の重版が刊行されました。
税込みで5千近くする本でありながら、初版の刊行から半年少しで重版が出るとは、予想外の売れ行きでした。ちょっと高額ですが、まだお手元にない方も是非ご購入ください。
■2017年3月24日、「国家論研究会」において「国民国家と外国人の権利 -1970・80年代ドイツの外国人政策を中心に」を報告しました。
もともと予定されていた報告者がやむを得ぬ事情で報告できなくなったため、急遽代役で報告しました。といっても、先月発表した論文の内容を簡略化して報告したものです。同内容の報告は、すでに昨年9月に「比較社会学研究会」でも報告しています。ただし、今回は前回の報告や論文では言及できなかったH.アレントやG.アガンベンの国民国家と人権との結びつきについての問題提起に触れました。
■2017年3月24日付の『琉球新報』に坂下雅一著『「沖縄県民」の起源 戦後沖縄型ナショナル・アイデンティティの形成過程 1945-1956』への書評が掲載されました。
著者の坂下さんは以前からの知り合いで、私が編集した本に論文を寄稿してもらったりもしています。今回は『琉球新報』からの依頼で、彼の博士論文を単行本にしたものへの書評を書きました。戦後のみならず、近代沖縄の「ナショナル・アイデンティティ」をとらえ直そうと試みた野心的著作です。(⇒閲覧可)
■2017年3月14日に、「国民国家と外国人の権利 -戦後ドイツの外国人政策から」が掲載された『社会志林』第63巻第4号が出版されました。
久々に『社会志林』に寄稿しました。同僚の奥武則先生(および他3名の先生方)の退職記念号ということで寄稿しました。しかし内容は、今年9月に報告した研究報告の内容を含まらせたものです。その論旨は、外国人政策も国民国家論の枠組みでとらえる必要があるという理論的含意をもったもので、既存の外国人問題への社会学的アプローチへの批判的な視点をこめているつもりです。「なぜドイツは(事実上の)移民国になったのか」「なぜドイツは世界有数の難民受け入れ国なのか」などの問題をとりあつかっています。
■2017年1月30日(月)に、立命館大学末川記念会館で行われた研究会「引揚げ/強制移住/故郷喪失」で、朴裕河さんの新著『引揚げ文学論序説』についてコメントしました。
韓国の日本文学研究者、朴裕河さんが最近取り組んでいる引揚げ文学に関する論考をまとめた『引揚げ文学論序説』を受け、戦後日本の引揚げにとどまらず、広くヨーロッパでの強制移住や故郷喪失について考ええる考える研究会でした。朴さんの著作にコメントした「ゲスト」は、私の他に日本の植民地法制史を研究している政治史研究者の浅野豊美さん、ポーランド文学を研究している田中壮泰さん、ドイツ文学の永畑紗織さん、フランス植民地文学などを研究している鵜戸聡さんと、文学研究者を中心に様々な分野の人たちでした。「ゲスト」からのコメントや報告に対し、朴さんが応答するという形式で行われました。
この研究会は、有名な比較文学者の西成彦さん(立命館大学)が、朴さんの新著をめぐる2日間の研究会の2日目です。以前、一度だけ別の研究会でお会いしたことのあった西さんから年末に突然メールをいただき、この研究会にお誘いを受けました。朴裕河さんは、『帝国の慰安婦』など、日本ではもっぱら従軍慰安婦問題での発言で知られている(数日前に、めでたく韓国で無罪判決が出ました)のですが、近年日本の引揚げ文学について研究を進められています。日本では、これまで「引揚げ文学」というくくりで研究が行われたことはないそうです。
文学のみならず、日本の引揚げはこれまで歴史学や社会科学の分野でもほとんど取り上げられてこなかったテーマだと思われます。私はかつて『ナショナル・アイデンティティと領土』(2008年)を執筆したとき、ドイツの「追放」との比較で日本の引揚げについて調べましたが、ほとんどまとまった研究がないことに驚いたものでした。その点で、今回の機会に送っていただいた朴さんの著作を読んで、日本における「引揚げ」という問題のフレームの欠落を鋭く指摘した議論に、「やはりそうだったんだ」と気が付くとともに、共感を覚えました。
また、文学のみならず歴史学の分野で、「引揚げ」というテーマに近年、関心が高まりつつあるらしいことを知り、興味を覚えました。今後の研究動向に注意を向けていきたいと思いました。
私のコメントは、「引揚げが戦後の日本で「公的な記憶」ないし「国民の物語」として残ることがなかった」という朴さんの指摘を踏まえ、ドイツでの「追放」の語りや記憶のされかた、「追放」をめぐる政治と論争について簡単に日本の「引揚げ」と比較しながらコメントしました。ドイツでは「被追放者諸団体が「故郷権」ということばを用いたことを紹介したのですが、これが参加された多くの方に興味をもっていただいたようです。失った故郷に対する「権利」を主張するとはいったいどういうことなのかという点、またそれが集団化され、ナショナリズムとして作用することの危うさについても問題になりました。私にとっても、とても刺激的な研究会でした。
■2016年10月27日に博士課程の大学院生諸君と一緒に編集し、翻訳したロジャース・ブルーベイカー著『グローバル化する世界と「帰属の政治」 移民・シティズンシップ・国民国家』(明石書店)が出版されました。

2001年以降にブルーベイカーが公刊した論文のなかから、移民、シティズンシップ、国民国家に関連する論文、「認知的視座」を論じた論文を独自に選んで翻訳しました。編訳者は私のほかに高橋誠一君、岩城邦義君、吉田公記君です。専門家のあいだではかなり知られているにもかかわらず、あまり内実がよく知られていないブルーベイカーの議論・アプローチを広く知っていただきたいためにこの本を編集・翻訳しました。学部・大学院生レベルでも十分に読める本だと思います。
1つはネーションや国民国家を中心においたアプローチ、もう一つは彼が「認知的」と呼ぶアプローチが独自な視点です。ブルーベイカーは私の博士論文の指導教員であり、私が現在に至るまで最も影響を受けた社会学者ですが、今回の翻訳を通じてあらためて彼の視点を深く納得することができました。今後、彼のアプローチを私なり展開しつつ、研究を深めていきたいという思いを新たにしました。
最後にかなり長文の「編訳者解説」を書いています。翻訳書にこのような解説文を書くのは「屋上屋」になってしまうかもしれないのですが、ブルーベイカーのアプローチをわかりやすく解説しようとおもってあえて書きました。
こちらから購入できます。⇒
■2016年10月9日(日)、九州大学伊都キャンパスで開かれた日本社会学会大会で「ロジャース・ブルーベイカーの認知的アプローチ ―その人種・エスニシティ・ネーション研究にとっての意義―」を報告しました。
2000年代にブルーベイカーが提唱している「認知的視座」について報告しました。経験的な志向が強い研究分野なので、私の理論的な報告が「浮いて」しまうのではないかと懸念していたのですが、思っていた以上にフロアの議論とのかみ合いがよかったという印象でした。フロアには15人程度(最大時で)しかいませんでしたが、議論もかなり活発でした。
近日中にブルーベイカーの翻訳本を出版しますが、その宣伝もしてきました。
■2016年9月18日、大阪にある神戸大学梅田インテリジェントラボラトリで開かれた比較歴史社会学研究会において「国民国家と外国人の人権 ――戦後ドイツの外国人政策から」を報告しました。
この「比較歴史社会学研究会」は、東京都立大学名誉教授の水林彪先生を中心として立ち上げられたもので、ヴェーバーを「知の交流点」としつつ、社会諸科学の様々な分野の研究者が交流できる場をつくろうということを目指した研究会です。今回私は、この研究会のメンバーである橋本直人さん(神戸大学)に依頼されて報告しました。研究会は毎年1回開催ということで、今年のテーマは「(国民)国家と人権」とされ、私のほかに奈良教育大学の佐野誠さんがヴェーバーにおけるパーリア概念とユダヤ人の問題について報告されました。
私の報告は、戦後欧米先進諸国の国民国家においてなぜ外国人の権利が認められるようになったのかを、「人権」と「民主主義」という二つの要素をもった「リベラルで民主的」な国民国家の「リベラル・パラドックス」との関連で考察したものです。具体的な事例として、主として1970年代から90年代にかけてのドイツ連邦共和国の外国人政策を検討しました。
参加者は15名弱ほどでしたが、ヴェーバー研究の大家折原浩先生と久しぶりに対面できたこと、水林先生のほか、東京外語大学名誉教授の中野敏男先生など、これまで著作を通してしか触れてこなかった方々とお会いでき、議論できたことはとてもいい経験でした。
今回の報告は、少し手直ししていずれ論文化することを考えています。
■「テクスト解釈学と文化社会学 ――「行為をテクストとみなす」という方法をめぐって」が掲載された鹿島徹・越門勝彦・川口茂雄編『リクール読本』(法政大学出版局)から7月25日に公刊されました。

ポール・リクール70年代の「テクスト解釈学」とジェフリー・アレクサンダーらを中心とするアメリカの「文化社会学」との関係を論じながら、社会的行為における「意味」の問題を「超主観的=「客観的」に扱う方法としての「テクスト解釈学」の方法について論じています。結論としては、70年代のテクスト解釈学は社会学の方法論としては不十分であるものの(テクスト概念が書かれた「作品」をモデルとしており、「読者―テクスト」関係の図式から出られていないこと)、その後のリクールの学的発展、特に晩年の『記憶・歴史・忘却』における「表象史」論(歴史学者ロジェ・シャルティエの方法)への接近は、十分に社会学的な方法論としての可能性をはらんでいるということについて論じました。シャルティエは「文化的転回」以後のフランス社会史の研究者です。
言うまでもありませんが、私はリクールの専門家ではなく、むしろ「ド素人」と言ってよいのですが、にもかかわらず編者の方から熱心に依頼され、自分でもリクールを新たに学ぶつもりで取り組んだ仕事です。私自身は、70年代初頭のリクールの数本の論文(しかもすべて英語で書かれた論文)しか知らなかったのですが、編者からの適切なコメントもあり、晩年のリクールの「物語」論への関心も膨らみました。
この『リクール読本』は、多作で関心の範囲が超人的に広いリクールという哲学者の姿が明瞭に示されたすばらしい作品になっています。私自身も学ばせていただくことの多い、優れた一冊です。編者の編集者の方に感謝です。
■2016年7月2日(土)、文化社会学講読会において「ロジャース・ブルーベイカーの認知的視座 -そのエスニシティ・人種・ネーション研究における位置づけと文化社会学的位置づけ」について―」を報告しました。
今、翻訳中のブルーベイカーの論文集に収録される「認知としてのエスニシティ」を中心に、彼の「認知的視座」についてまとめたものです。ほぼ同じ内容を、10月の日本社会学会大会でも報告する予定です。
■「「ドイツ人」概念の変容 ――「○○系ドイツ人」から考える」を、2016年5月25日発売の『移民・ディアスポラ研究5 マルチ・エスニック・ジャパニーズ ○○系日本人の変革力』(駒井洋監修 佐々木てる編著、明石書店)に掲載しました。

「移民の背景を持つ」人たちのあいだでドイツ国籍保有者が増え、移民第二世代が社会の中核に進出するようになるにつれ、「ドイツ人」概念が変化しつつあります。2000年から国籍法に出生地主義がとりいれられ、かつてのように前世代からのドイツ人の「血統」だけでは、「誰がドイツ人なのか」を決められなくなっています。にもかかわらず、出自に基づく「ドイツ人」認識は、先住ドイツ人のあいだでは依然として根強いものがあります。この論文は、最近ガウク大統領の帰化宣誓式での発言から始まり、「ドイツ人」概念をめぐるディレンマについて論じています。
『移民・ディアスポラ研究』に寄稿するのはこれが2回目です。毎号ホットなテーマをかかげて論文を集めて出版しています。特に今回は、前半に外国の事例をとりあつかった論文(アメリカ、ドイツ、シンガポールなどのアジア諸国)を並べ、後半に日本の「○○系日本人」の事例をあつかった論文を掲載しています。全体に一貫性があり、個々の論文も読み応えのあるものです。(⇒こちらから購入できます)
■2016年3月6日(日)、国家論研究会で「近年のドイツにおける排外主義とその政治・社会的背景 ―「イスラム批判」からPEGIDAまで―」を報告しました。
今年度から科研費で行っているドイツの排外主義研究の、今年1年間の「成果報告」になります。今世紀に入ってから、ドイツは「非移民国」から「移民国」への転換が進んでいますが、それ当時に排外主義も目立ってきました。この報告では2005年前後から台頭する言論人・知識人たちとメディアによる「イスラム批判」、2010年のザラツィン論争、そして2014年末に突如発生するPEGIDAの運動、そして昨年度右傾化が顕著となったAfDの動向を概観しながら、社会国家における資源の再配分問題をめぐる対立や不満が「反イスラム」という名の下での排外主義を動機づけているという仮説を検証しました。検証は不十分ですが、可能性はありそうな感覚はもつことができました。
なお、今回の国家論研究会は科研費の研究活動の一環であるとともに、来年度から私が「所長」をつとめることになる「グローバル化と移民問題研究所」(法政大学内のペーパー研究所です)の活動の一環でもあります。東北大学から永吉希久子さんをお招きし、福祉国家と排外主義の関係に関する計量的比較研究の報告をお願いしました。
■『Migrants Network(エムネット)』(2015年183号)に、「難民受け入れ国としてのドイツ」が掲載されました。

『エムネット』は、移住者支援を行っているNPO団体「移住者と連帯する全国ネットワーク」の情報誌です。この「移住連」は、弁護士や学者もメンバーとしてかかわり、毎年行政機関との「省庁交渉」も行っている、持続的に移住者の生活支援や権利保護の活動をおこなってきた全国レベルの移住者支援団体です。『エムネット』は最近から前頁カラーになり、格段に手に取りやすくなりました。この号は2015年になっていますが、昨年最後の号で、実際は1月に入ってから発行されました。
私が寄稿しているのは、見開き2ページの小文ですが、昨年100万を超えるといわれる庇護請求者(難民)を受け入れたドイツの難民受け入れ体制について簡単に紹介しています。ドイツの人口は現在約8000万人。そこに100万の難民(正式に「難民」として受け入れられるのはその一部ですが、難民申請の結果が出るまではすべてドイツ国内に滞在することになります)を受け入れるわけですから、その負担は半端なものではありません(日本に当てはめて考えてみればわかるでしょう)。しかし戦後のドイツには難民受け入れの歴史があり(もちろん、だれでも無条件に受け入れたわけではなく、様々な制限を設けても来ました)、国家としての受け入れ体制もそれなりに(決して「完璧」というわけではないですが)形成されてきました。しかし、その体制も現在大きな挑戦にさらされています。そのあり様について簡単に述べたものです。内容はすでに10月18日の国家論研究会で報告しました。
■2015年10月31日(土)、文化社会学講読会で「テクスト解釈学と文化社会学――「行為をテクストとみなす」という方法をめぐって――」を報告しました。
フランスの哲学者ポール・リクールの「テクスト解釈学」とジェフリー・アレクサンダーらの文化社会学の関係について論じたものです。法政大学出版局近刊の『リクール読本』に掲載される予定の論文の報告でした。
■2015年10月18日(日)、国家論研究会で「難民受け入れ国としてのドイツ」を報告しました。
『Migrants Network』12月号掲載予定の小文を報告しました。報告者の予定になっていた人がキャンセルになったので、急遽2日前に書き上げた文章を使いました。ドイツの難民受け入れ体制について説明したものです。今年は1年間で100万を超えようという難民(庇護請求者)を受け入れることになるドイツですが、果たしていったいどのように彼らを「受け入れ」ているのか、その限界はどこにあるのかについて、国家の体制に焦点を当てて概説したものです。現在ドイツでは、連邦政策の難民受け入れ政策に反対する声が次第に強まり、収容所への放火などの暴力事件も多発するようになりました。しかし、それをもってドイツの国家や社会が「反難民的」であるととらえるのは誤りだと思います。これまでの「経験から、ドイツは少なくとも年間数十万規模の難民を「受け入れる」法的・行政的体制をつくってきました。しかし、それへの負担も増大しているようです。難民受け入れの負担は地方(州・市町村)に向かうようになっていて、反難民の動きはその地方レベルから発しています。
■2015年10月9日、東京の紀尾井町にあるドイツ-日本研究所で開かれた日独社会科学学会で"Shifting risk perception of nuclear energy after Fukushima: The German nuclear phase-out and its cultural background"を報告しました。
日独社会科学学会は1990年にできた日本とドイツの社会科学者、心理学者からなる学会で、今年は第13回の大会になります。大会は1年おきに日本とドイツで交互に開かれています。私がこの学会で報告するのはこれで3回目になります(どれも日本で行われた時の大会です)。学会の公用語は英語になっています。今回の報告は、大会2日目の午後でした。大会は8日から10日の3日間行われ、報告者の数も多く、なかなか盛況でした。
内容は、随分前に書いたドイツ語論文"Restrisiko. Fukushima in Deutschland"とその後の研究成果である2014年6月にドイツ現代史学会での報告の内容を短く一つにまとめたようなものです。ここ1年間以上このテーマを放置してきたので、昔調べたこと、考えたことを思い出しながら、15分で報告できる内容にしました。このテーマを日本語の論文にしたいのですが、なかなか実現できないでいます。
久しぶりの英語での報告だったので、出だしに考えていたことを表現する英語が口から出てこなくなって少々あわてましたが(油断大敵です)、後はかなり作りこんだパワーポイントと一応書き出した原稿をもとになんとかわずかの時間超過で報告ができました。
時間の関係で質問に1つしか答えられず、どのような反応(とくにドイツ人の参加者の)が気になっていましたが、終わった後の懇親会で、会長のTrommsdorffさんと前会長のKornadtさんがわざわざ私のところに来て「大変よい報告だった」と褒めていただき、Kornadtさんからは「福島の事故に対するドイツ人の反応については申し訳ない」と(半分冗談ですが)おしゃっていただきました。この研究自体が、2011年3月にコンスタンツ滞在中の経験に端を発しているだけに、わかっていただけたようだ、と安心しました。
■2015年9月発行『社会学評論』Vol.66,No.2(2015)に書評「昔農英明『「移民国ドイツ」の難民庇護政策』(慶応大学出版会、2014年)」が掲載されました。
この本は、「教会アジール」に焦点をあてたユニークなドイツの難民庇護政策分析です。今年百万人もの難民を受け入れることが見込まれているドイツの難民政策は日本でも注目が集まっていますが、国家によって庇護を拒否された庇護希望者をかくまう「教会アジール」はドイツ社会の「懐の深さ」を感じさせる興味深いものです(庇護している難民の数は多くないのですが)。
■雑誌『プレジデント』2015年8月31日号に、に私の取材に基づいて書かれた記事「移民受け入れ:なぜドイツは、国力アップに活用できたのか」が掲載されました。
『プレジデント』は名の通った経済誌です。同誌と契約しているフリーライターの小澤啓司さんという方がが私の取材に基づいて書かれた記事です。取材は約1時間半ほど行われました。このような雑誌に移民関係の記事が載るということは、経済界も日本の移民政策について関心をもっているということを示唆しているでしょう。私は、単純に現在の日本とドイツの状況を比較してあれこれという前に、ドイツは1950年代から外国人労働者を受け入れていた歴史があり、いい意味でも悪い意味でも「経験」をもっているということを強調しました。日本がドイツの移民政策を参考にしようというのであれば、その戦後半世紀以上に及ぶ「経験」を見てみる必要があります。
ここから(⇒)この号の目次を見ることができます。
■2015年6月28日(日)、京都大学文学部で開かれた第55回日本社会学史学会大会シンポジウム「社会学理論の最前線 -時間-」で、「討論者」として登壇しました。
今年の日本社会学史学会は6月27~28に開かれましたが、シンポジウムはいつも通り二日目の午後に行われました。テーマは「時間」。若手・中堅の研究者が「時間」をテーマに報告し、私はその後「討論者」として報告に対するコメントをしました。
報告は多田光宏さん(熊本大学)による「社会学の基本概念としての時間 -現象学的社会学と社会システム理論の観点から-」、伊藤賢一さん(群馬大学)「批判理論としての社会的加速化論 -Rpsa理論の射程-」、濱西栄司さん(ノートルダム清心女子大学)「アクターの経験と時間 -トゥレーヌ派S.Tabboniの議論を中心に-」の三つで、討論者は私の他に三上剛史さん(追手門学院大学)でした。司会は森元孝さん(早稲田大学)、出口剛司さん(東京大学)でした。
「時間」という切り口から、最近の社会学理論を展望することのできた、意義深いシンポジウムでした。
■2015年3月31日付で近藤潤三著『書評:ドイツ移民問題の現代史――移民国への道程(木鐸社、2013年)』がドイツ現代史研究会の雑誌『ゲシヒテ』第8号に掲載されました。
近藤氏はドイツの移民問題を丹念に研究してきたベテランの研究者です。本書は、氏のこれまでの研究を踏まえ、ドイツの専門家以外の読者にも読めるような「概説書」を意図して書かれています。近藤氏の著作はこれまでもしばしば参照させていただいていたので、今回この本の書評を依頼されたことをとても光栄に感じています。氏のスタイルはオーソドックスな歴史的研究なので、社会学者の「理論的」視点から見ると色々と「突っ込みどころ」が見えてきます。そのようなところを中心にやや批判的に書かせていただきましたが、氏の研究の重要性は疑いのないところです。
なお、日付は3月31日ですが、実際刊行されたのは6月でした。
■2015年4月13日付で樋口陽一著『加藤周一と丸山眞男 日本近代と〈知〉と〈個人〉』(平凡社、2014年)の書評が『公明新聞』に掲載されました。
私が言うまでもないことですが、樋口陽一氏は高名な憲法学の大家です。私は氏の著作をほとんど読んだことはなく、この著作が出版されたことも知らなかったのですが、『公明新聞』(公明党の新聞ですが、私自身は公明党とは一切関係がありません)から書評を依頼をされました。加藤周一と丸山眞男を再読しながら、立憲主義の立場に立った日本の国家像を探ったものです。この本の書評を書くのに、これまでほとんど関心がなかった加藤周一の著作(特に雑種文化論など)に目を通してみました。全体は800字なので、あまり多くのことは書けませんでした。ですが、わりといい勉強になったと思っています。こちら(⇒)から新聞紙上の私の書評をスキャンしたものをみることができます。
■2015年3月30日付で刊行された宮田眞治・畠山寛・濱中春編『ドイツ文化55のキーワード』(ミネルヴァ書房)に「連邦制」(項目)、「EUのなかのドイツ」(コラム)を寄稿しました。

題名通り、ドイツ文化を紹介する55項目について解説したものです。その他、「コラム」が数個ついています。各コラムは具体的な「モノ」やコト」にこだわっています。ちょっと上級向けの観光ガイドのようなものであり(たとえば「ウィーンフィルとベルリンフィル」のような項目もあります)、どの項目も大変に魅力的です。そのなか、私が分担している「連邦制」はもっとも退屈な項目に入るでしょう。言い訳になりますが、「連邦制」を具体的にとりあげるのは、結構難しかったのです。結局、連邦参議院についてとりあげ、これを中心に解説しました。
■2015年3月18日付で宮島喬・小ヶ谷千穂との編著『国際社会学』が有斐閣から出版されました。

1990年代ころから日本で使われるようになった「国際社会学」(英語でいうとtransnational sociologyです)の教科書です。これまで、どちらかというとインターディシプリナリー(学問領域横断的)な領域とみなされがちだった「国際社会学」を、本書ではあくまで「社会学」の一分野として打ち出すことを目指しています。執筆者も全員社会学者です。社会学の理論枠組み、社会学の基本的下位分野(家族、社会階層、ジェンダーなど)の方法論を用いて、国境を越えた「トランスナショナル」な社会現象を分析した研究成果を紹介したものです。私はこの中で、第1章「国民国家とシティズンシップの変容」を分担し、また他の編者の方たちと一緒に序章を執筆しています。その他、「ナショナリズム」と「グローバル化」のコラムを書いています。
全体の構成は以下の通りです。
序 章 国際社会学に向けて─現代社会へのトランスナショナルな接近
第1章 国民国家とシティズンシップの変容
第2章 トランスナショナルな移民ネットワーク
第3章 労働市場と外国人労働者の受け入れ
第4章 階層構造のなかの移民,マイノリティ
第5章 グローバル化と家族の変容
第6章 グローバル化のなかの福祉社会
第7章 移民/外国人の子どもたちと多文化の教育
第8章 人の国際移動とジェンダー
第9章 途上社会の貧困,開発,公正
第10章 在日朝鮮人一世のジェンダーとアイデンティティ
第11章 「ヒスパニック」を通してみるアメリカ社会
第12章 フランス移民第二世代のアイデンティティと教育
ぜひ、手に取ってご覧ください。(こちらから購入できます⇒)
■2015年3月15日(日)第59回数理社会学会シンポジウム「排外主義への社会学的アプローチ」において、「排外主義と国家 ―国家中心的アプローチの試み-」を報告しました。
第59回の数理社会学会大会は久留米大学御井キャンパスで3月14・15日に行われましたが、大会シンポジウムは大会2日目(10:50~12:50)でした。私自身はこの学会の会員ではないし、「数理社会学」は全くの素人なのですが、今回は早稲田大学の田辺俊介さんからの依頼で報告を引き受けました。私も最近、ドイツの排外主義について関心をもっているので、今考えているところをまとめてみました。「国家中心的」というのは、最近の私の「国家」をめぐる論考(下記『国家の社会学』で展開しています)を基本にしたアプローチです。しかし今回は、「集合財collecive
goods」という、『国家の社会学』のなかでは使わなかった概念を軸に「国家論的」なアプローチを構想してみました。「集合財」というアイデアは、アンドレアス・ウィマーの議論からの影響を受けています。
シンポジウムは、
司会:樽本英樹(北海道大学)
報告者:
佐藤成基(法政大学)
排外主義と国家 -国家中心的アプローチの試み-
Kim Jae-Woo(Chonbuk National University)
Group Identity, Trust and Cooperation : What We Have Learned from Formal Models & Implications for Issues in Multicultural Society
田辺俊介(早稲田大学)
計量モデルからのアプローチ:概念モデルをベースにした検討
という組み合わせで行われました。報告は、「三者三様」という感じで、排外主義に関する多様なアプローチが紹介されました。
■単著『国家の社会学』が2014年12月25日に青弓社から刊行されました。
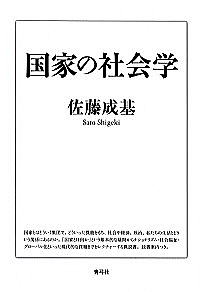
構想からなんと3年もかかってしまいました。国家に関する社会学的な視点からの概説書です。全体は「はじめに」と「おわりに」を前後に配し、15章からなっています。マックス・ヴェーバーの国家概念を基点しつつ、チャールズ・ティリー、マイケル・マン、シーダ・スコッチポルといった現代の英語圏の社会学者による国家論に依拠しつつ、国家を独特な制度的実在ととらえ、その独自な能力と社会に対する作用について様々な観点から論じています。
全体の構成は以下のようになっています。
はじめに なぜ、「国家」なのか
第1章 国家とは何か -その能力と作用
第2章 国家と暴力 ―マックス・ヴェーバーの国家論
第3章 国家と官僚制
第4章 国家と戦争 ―国家形成における軍事的・財政的要因
第5章 国家と正当性 -「象徴暴力」と公共性
第6章 国家と社会 ―社会の「国家帰属化」
第7章 国家と統計(学)
第8章 国家とナショナリズム
第9章 国家と資本主義経済
第10章 国家と民主主義
第11章 国家と社会福祉
第12章 国家のグローバル化
第13章 脱植民地化と「崩壊国家」 -アフリカ国家論の観点から
第14章 グローバル化のなかの国家
第15章 国家の現在、国家の将来
おわりに 多形体的実在としての国家
ぜひ、多くの方にご一読いただきたいと思っております。(⇒こちらから購入できます)
■「移民政策」を寄稿した西田慎・近藤正基編『現代ドイツ政治――統一後の20年』が2014年11月15日にミネルヴァ書房から刊行されました。

11月9日、ドイツではベルリンの壁崩壊25周年を盛大に祝っていました。本書はそれとほぼ同時に刊行されました。厳密にいうと、今年はドイツ統一後24年目ですが、本書はドイツ統一後の政治について若手中堅のドイツ研究者が集まってつくった大学生・大学院生向けの教科書です。執筆者は編者2人を合わせて10人です。私は「移民政策」の章を書いています。
意外にこの種の本は多くありません。ドイツ政治について少しでも知りたいひとにとっては、学生であるとないとにかかわらず、とても便利なテキストになっていると思います。
全体の構成は以下の通りです。
序 現代ドイツ政治とは何か
Ⅰ ドイツの政治力学
1 キリスト教民主・社会同盟
2 社会民主党
3 緑の党
4 左翼党
5 自由民主党
6 労使関係
7 EUとドイツ
Ⅱ ドイツの政策展開
8 外交政策
9 福祉政策
10 家族政策
11 脱原子力政策
12 移民政策
現代ドイツ政治関係資料
奇をてらわない、実に堂々とした構成です。必要なことはほとんど網羅されています。各章も充実しており、かつてのドイツ研究にありがちな(今でも一部残っていますが)「偏り」(どうしても左翼的な視点に偏ってしまう傾向があり、そのため、ドイツ政治の保守的側面などが過小評価されてしまう面がありました)もみられません。
もちろん時代とともにドイツ政治は変化しますが、かなり長い間ドイツ政治の基本文献として読まれることを期待しています。
こちらから購入できます。
■"Territorial disputes and national identity in postwar Germany: The Oder-Neisse line in public discourse"がEuropean Journal of Cultural and Political Sociology, Vol.1, No.2(2014年9月刊)において刊行されました。
2008年に刊行した拙著『ナショナル・アイデンティティと領土』の英語による縮約版といってよいでしょう。実際に執筆したのは5年ほども前でした。何度か学会や研究会で配布した英語のペーパーが元になっています。刊行まで長い時間がかかったのは、査読審査に手間取っていたからです。最初は別の某雑誌に投稿しましたが、査読になんと2年半もかかったあげく「没」にされてしまいました。そこで別の雑誌に投稿してみたら「雑誌のテーマに合わない」ということで査読に入る前に拒否され、今回掲載された雑誌に投稿したのが約1年前でした。そして、ようやく刊行にいたったわけです。Euroepean Journal of Cultural and Political Sociologyは最近ヨーロッパ社会学会が立ち上げた新しい学会の公式雑誌です。ドイツ研究の専門誌ではないこと、なるべく「社会学」の専門雑誌であること、できればアメリカではなくヨーロッパに拠点を置いた雑誌であり、ヨーロッパに詳しい研究者がかかわっていることが私の投稿先の条件でしたが、この雑誌はこの条件にピッタリしたものです。

査読審査の過程では、ここには書けないような面白い、あるいは腹の立つ経験をしましたが、結果として刊行までに計6名もの匿名の研究者の査読を経たことで、オリジナルなものがかなりブラッシュアップされた気がしています。2008年の拙著には書けなかったそれ以後の状況についての記述や、理論枠組みの発展なども盛り込まれています。
こちらから、論文がダウンロードできますので、関心のある方は見てみてください。
■2014年7月16日(水)、パシフィコ横浜で開かれた国際社会学会(International Sociological Association)の第18回世界大会(World
Congress of Socioloy)でマサリク大学(チェコ)のWerner Binder氏と共同でShifting Risk Perception after Shocking Events: Counter-Terrorism in the
United States and Energy Policy Change in Germanyを報告しました。
日本社会学界あげての大イベント、ISA世界大会は7月13日(日)~19日(土)に開かれました(⇒)。私は完全にフリーライダーで、単に報告をしただけでした(もうひとつ、別のセッションで司会もしました)。しかし、大会をオーガナイズした方々は大変だったと思います。なかなかよい世界大会だったと思います。ただ、われわれが報告した展示ホールの中に特設されたブースは、周りのブースの報告が響いてしまい、とても報告しにくい劣悪な環境ではありました。われわれが報告したのは、Thematic Group
4の枠内で開かれたセッションでした。
報告は、かつてコンスタンツ大学在外研究中に知り合った友人であるWerner Binder君と一緒に行っている研究の途中経過です。「衝撃的事件」とそれによるリスク概念の変化を、文化社会学的に分析しようというもので、911以後のアメリカと311以後のドイツとを比較しています。研究結果は近いうちに論文でまとめて、どこかに投稿する予定にしています。
■2014年6月21日(土)、ドイツ現代学会研究例会(京都・キャンパスプラザ)にて「原子力とリスク認知 ―ドイツ脱原発の文化社会学的考察―」を報告しました。
ドイツ現代史学会は、関西系の研究者によって組織されているドイツ近現代史を中心とした研究会です。発足は1968年だそうですから、かなりの歴史のある研究会です。私は会員ではないのですが、神戸大学の近藤正基さんに依頼されて報告をしました。最近、ドイツ研究関係の人たちから誘われることが多くなっています。報告は、最近はじめたドイツの脱原発問題の歴史的かつ文化社会学的研究の中間報告的なものです。ドイツロマン主義に起源をもつ「文明批判」論と、現代ドイツのエコロジー運動や環境政策との間の関係性を考察し、ドイツの「緑」の特殊性の文化的ルーツをたどろうという、かなり「ベタ」な議論をやっています。近いうちに論文にもする予定でいます。
同日には静岡大学の高岡智子さんの東ドイツにおけるポピュラー音楽についての興味深い報告もありました。
(追伸:同名のタイトルの論文を現在執筆中です)
■書評「国民国家への挑戦(書評対象書:樽本英樹著『国際移民と市民権ガバナンス――日英比較の国際社会学』)」が『現代社会学理論研究』第8号(2014年3月31日付)に掲載されました。
北海道大学の樽本英樹さんの近著への書評論文です。樽本さんはミネルヴァ書房から『よくわかる国際社会学』をすでに上梓していて、日本の国際社会学を代表する社会学者です。この書評では、国際社会学が広く共有している「国民国家ヘの挑戦」という視角のもつ盲点について指摘したつもりです。
■「領土と国益 ――ドイツ東方国境紛争から日本を展望する」が『ドイツ研究』第48号(2014年3月25日付)に掲載されました。

昨年6月に行われた日本ドイツ学会のシンポジウム「領土とナショナリティー」の報告に基づく論文です。すでに「解決」されたドイツの東方国境紛争といまだ係争中の日本の領土紛争を比較して、何が違うのかを考察したものです。最後に、「領土の保全=国益」という図式に疑問を投げかけ、もっと広い視点から「国益」をとらえなおす必要性を示唆しています。例えば、北方領土に関して「四島返還」を国是にすることが、本当に日本の「国益」に資することになるのか、ということです。論文の中では明記しませんでしたが、日ソ共同宣言に書かれている歯舞・色丹だけで妥結して国後・択捉は譲り、その譲歩をなるべく「高く売りつける」ことで北方地域の共同開発をねらう。つまり「二島プラスα」案で、その「α」には領土は含まないという妥結の仕方が最も現実的だと考えています。国後択捉にはすでに多額のインフラ投資がなされており、ギリシャ正教会の教会もつくられているとのことです。この地域はもちろん、戦後ロシア人が「入植」してきた土地ですが、すでに70年近くがたち、今更ここを日本に「返還」するというのは無理な話です。しかも日本人は1人も住んでいないのです。最近クリミア半島での住民投票を根拠に、ロシアがここを併合しましたが、このやり方を仮に行った場合、国後択捉が日本に帰ってくる可能性はほとんどありません。日本ではいまだに、この土地が「いつか帰ってくる」と漠然的に考えて日露関係の将来を考えている人が多いように思いますが、そろそろそのような夢から覚めるべきでしょう。私は数は少ないですが何人かロシア人の知人・友人がいます。どの人もリベラルな感性の持ち主ですが、北方領土の話をすると「ロシアがここを返すとはとても考えられない」と即座に答えが返ってきます。そのくらいの時間が、すでに経ってしまったということです。
この雑誌には他に、ポーランド研究の吉岡潤さんの「失われた東部領/回復された西部領」というとても貴重で興味深い論文も掲載されています。戦後西に大きく動いたポーランドの領土問題を論じたもので、私がこれまでドイツの側から見てきた現象に裏から光を当てていただいた感じがしました。その他に、ルーマニアのドイツ語系文学の藤田恭子さん、著名なドイツ法の専門家広渡清吾先生の「領土と国籍・市民権」、日本語の堪能なドイツ人の日本研究者ラインハルト・ツェルナーさんのヘルゴラント島と竹島の比較論も載っています。そしてコメントは、気鋭のドイツ現代史研究者の川喜田敦子さんが「近代国家における人と土地」という視点からタイトルでつけています。(本号の概要についてはこちらから⇒)
■「ドイツの排外主義 ――「右翼のノーマル化」のなかで」を寄稿した小林真生編『移民・ディアスポラ研究3 レイシズムと外国人嫌悪』が出版されました(2013年10月)
ヨーロッパ諸国で広くみられる「右翼ポピュリズム」の台頭(反移民・反イスラムと反ヨーロッパ統合を求める)を「右翼のノーマル化」ととらえ、ドイツの「右翼ポピュリズム」の現状を考察したものです。ドイツは周辺諸国と異なり、有力な右翼ポピュリスト政党が存在しませんが、2010年の「ザラツィン論争」がそれに相当する役割を果たしていたという点を論じています。なお「右翼のノーマル化」は、社会学者のメーベル・ベレジンの最近の研究からとった概念です。「極右」と呼ばれていた勢力が社会のメインストリームに浸透してくるとともに、旧来の人種主義的・反民主主義的な側面が後退し、国民の利益やヨーロッパ文明、リベラルな民主主義的規範の尊重を主張するようになってきている傾向を示しています。「右翼」はもはや「極端」な(異端な)主義主張ではなくなっているということです。
小林真生さんが編集にあたっている『移民・ディアスポラ研究』の第3号は、第1部が「レイシズムとしてのネット右翼。、第2部が「ヨーロッパにおけるイスラモフォビア」、第3部が「日本人の排外意識と外国人管理の強化」となっていて、私の論文は第2部に入っています。第1部では安田浩一氏の対談なども収録され、全体として最近の日本のヘイトスピーチやネット右翼の問題を、ヨーロッパとの比較や歴史的な視点で一望できるようになっているので、この問題に関心のある方にはお勧めです。
こちらから、目次が読めるようになっています⇒。

■2013年10月12日、第86回日本社会学会大会(慶応大学)の研活テーマセッション「リスク社会論再訪」で、「「残余リスク」――福島原発事故とドイツにおけるリスク認知の変容――」を報告しました。
あらためて数えてみると、日本社会学会で報告するのは12年ぶりでした。やはり社会学者を生業としているかぎり、日本社会学会では報告するものだとあらためて思いました。内容は、ドイツ語で書いた論文“Restrisiko.
Fukusihma in Deutschland"(下記)を簡略化したものです。20分で報告できるように工夫をしました。
この部会は北海道教育大学の小松丈晃さん(『リスク論のルーマン』を書かれた方)がオーガナイズしたものです。これまでリスク論とは全く無縁だった私にとっては、このセッションで報告するのはとても新鮮な感じがありました。また、リスク問題についての社会学的考察も理論面・実証面で色々と蓄積があるのだなと思いました。私の報告したドイツのリスク認知の話にも関心を持っていただき、報告のし甲斐がありました。もう少し、このテーマを追求して行こうと思っています。
■『図書新聞』2013年9月14日号に丹野清人著『国籍の境界を考える ――日本人、日系人、在外外国人を隔てる法と社会の壁』(吉田書店、2013年)の書評を掲載しました。
日本の国籍法における「血統主義」の意味とその変化について論じている著作です。国籍という問題に関心のある方にはおすすめです。こちら(⇒)から購入できます。
■"Restrisiko. Fukushima in Deutschland"を掲載したKay Junge, Werner
Binder, Marco Gerster und Kim-Claude Meyer (Hg.), Kippfiguren. Ambivalenz in Bewegung (Velbrück Wissenschaft, 2013)が出版されました(2013年7月)。
コンスタンツに在外研究中にお世話になったギーゼン教授の弟子筋の人たちが編集している論文集で、ギーゼン教授の65歳の誕生日(5月)に合わせて出版される予定でしたが、出版社の怠慢とかで、2か月遅れてようやく出版されました。
テーマは311以後福島第一原発事故がドイツの脱原発政策に与えた影響についてです。原発問題もエネルギー問題も、私がこれまでまったく取り組んだことのないテーマでした。しかし、私がドイツ滞在中の実体験から、このテーマについて一本論文を書いてみたいと思っていたところ、ちょうど今回の論文集の話をいただき、ちょうどこのテーマが本の全体のテーマにフィットするようなので、あえてドイツ語で論文を書いてみたものです。論文のタイトルを訳すと「残余リスク:ドイツにおけるフクシマ」になります。福島原発事故によってドイツにおける原発の「リスク認識(Risikowahrnehmung)」がいかに変化したのかを、1970年代から現在までの原発政策の論議を素材として、「文化社会学的」なアプローチを用いながら(ギーゼン先生の著作も引用しつつ)明らかにしたものです。「残余リスク」という概念は、、日本ではあまり知られていませんが、ドイツでは以前からしばしば言及される有名な概念で、科学技術をもってしても排除できない極めて小さなリスクのことを意味しています。
福島原発の事故以後、日本では「脱原発」対「反原発」の対立が明確化し、原発について話をするときには必ずどちらかの立場に立たなければならいようなプレッシャーが強くなっています。私はこの論文のなかで、できうる限りこの両者のどちらの立場にも立たず、対立構図から脱するようなスタンスから書いてみました。「こうすべきだ」「「こうすべきではない」というような規範的あるいは政治的な主張(それはしばしば二項対立の構図に嵌められて主張されるのですが)からできる限り距離を置いて分析するというスタンスは、私が社会学者として常に心がけているものです。
ドイツ語ですが出版社による説明がここで読めます(⇒)。本のタイトルの“Kippfiguren”とはだまし絵(見方によって二通り以上のイメージが読み取れる絵)のことです。例えば、下のような絵が有名です。

副題の「動く両義性」が指し示しているように、社会的現実は常に両義的なものであるということが、この「だまし絵」に含意されています。といっても、これだけでは何のことだかはよくわからないでしょうが・・・。
本の中に中10以上もの比較的短めの論文が集められています。すべてギーゼン先生の研究室に出入りしている(していた)人ばかりです。どの論文も社会的現実の両義性について論じています。
amazon.co.jpでの購入はこちら(→)です。
※論文は「研究業績」のページからダウンロードできます。


●トップページに戻る